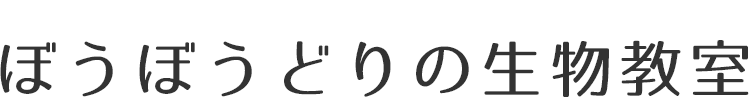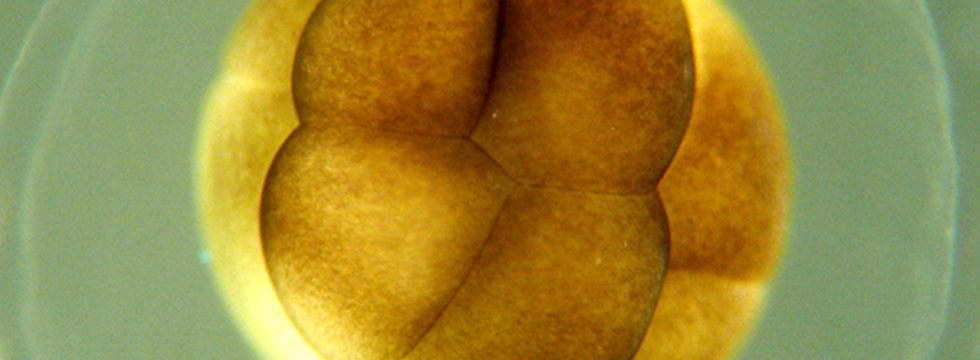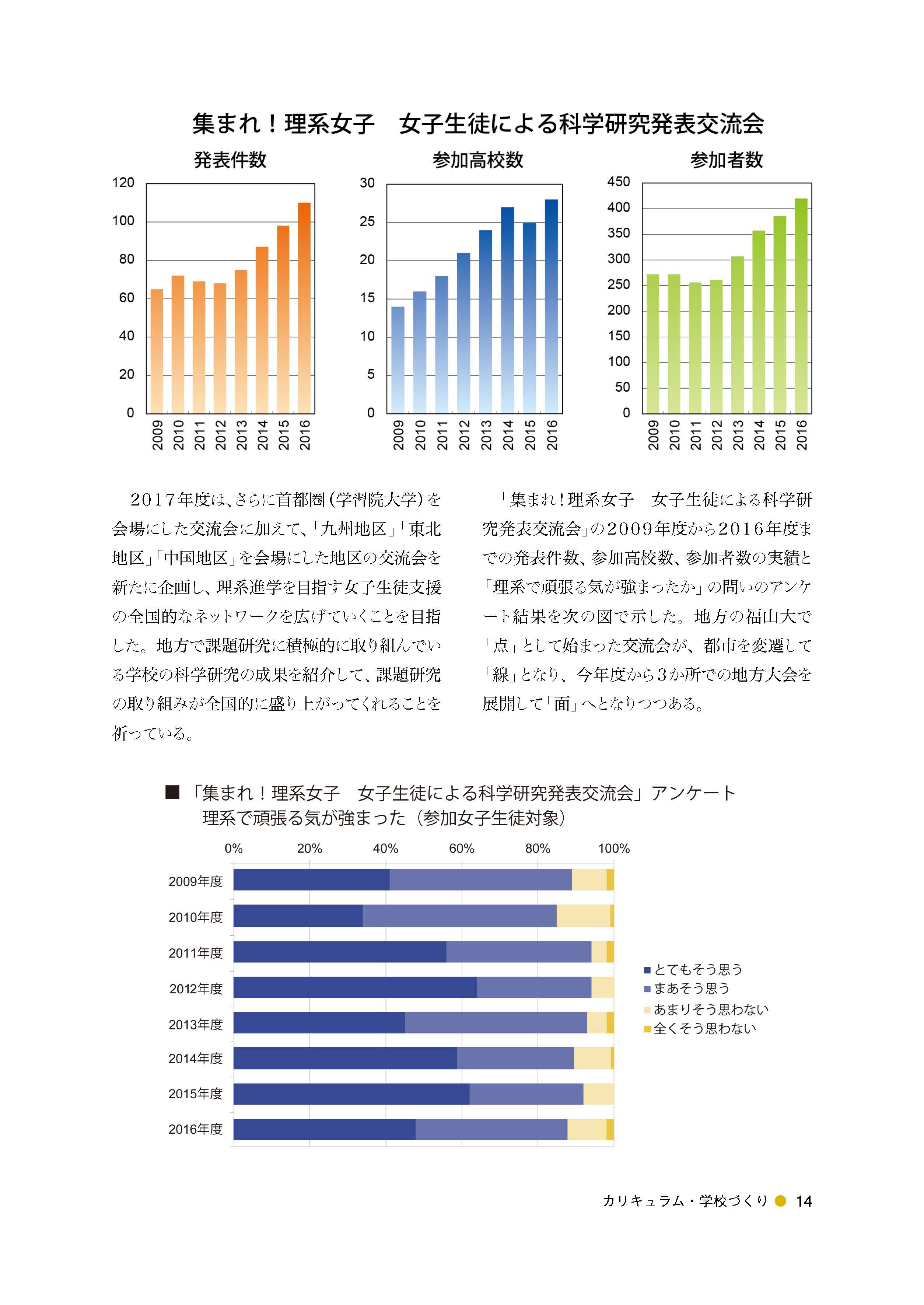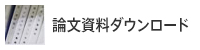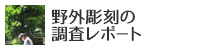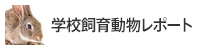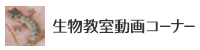自宅の本棚から『知能神話』(山下恒男編)を取り出して、ページを捲っていたら小沢牧子さんの書いた部分に以下のような箇所があった。
“わかる”とか“できる”というのはいったいどういうことなのだろう。子どもとつきあっているときに、しばしばこのことを考えさせられる。子どもがものと親しくふれ合いながらそれを自分の中にとらえこんでいく営みは、実に多面的で豊かな顔をもっているからだ。
たとえば、幼稚園児は同じ椅子がたくさん並んでいる中から、自分の椅子をちゃんと見分けることができる。家庭の中でも、数人のきょうだいが大人には同じようにみえるハソカチや消しゴムを、「自分のはこれだ」と迷わずに“わかって”いる風景はよくあることだし、父親が自動車で帰宅したときに、「あっ、お父さんの車の音だ!」とすばやくその音を聞き分けるのも、たいてい幼い子どもである。
ものと子どものこういう親密な“わかりかた”は、心理学者ウェルナーが「相貌的知覚」と名づけた知覚のスタイルに属している。(『精神の発達』岩波書店)
それはふつう、「原始的な」心性とよはれている。このような“わかりかた”は単に子どもばかりではなく、「原始的な」心性をもつといわれる人々、たとえばアフりカの原住民などにもみられる。彼らが抽象的な数としては“3”くらいまでしか理解しないにもかかわらず、数百頭の牛のなかの一頭がいなくなったことをすぐに発見する能力がそれに当る。数百頭の中の失踪した一頭は、数としての1ではなく、その牛なのである。そのような“わかりかた”のできる人々にとって、抽象的な高度な数概念は生活の中に必要とされない。そして彼らのもつ能力は逆に、西欧近代文明の中に生きる私たちの中からは非常にうすれてしまったものである。私たちは“わかる”という言葉を、しばしばたいへん気易く使っているけれども、少し立ち止って考えてみると、この言葉はなかなか深い問題をもっていることがわかる。
ピアノを教えているある母親が、「算数の勉強がわかるとは何か」を話しあう親たちの集まりで、次のように発言したことがある。
「子どもにピアノを教えていると、4分の1拍子とか3分の1拍子とかいうリズムがいきいきとわかる子どもは、算数の勉強などはあまり得意でないことが多いのだけれど、逆に分数をすらすらとこなすような子どもは、3分の1や4分の1といったリズムを身体でとらえることが昔手みたいなのです」
この指摘は、単に音楽が得意、算数が得意というような個人差のレベルだけではなく、もう少し深い問題を含んでいるのではないだろうか。この集まりに同席していた数学者弥永健一は、後にその会へ寄せた手紙の中で次のように述べている。
「分数計算ができてもリズムがつかめない、またはその逆にリズムはつかめても分数計算ができない子どもが多いということは、分数について“わかる”ということがそれ程簡単なことではないということを示しているのだと思います。2分の1、3分の1・・・について“わかる”ということは、ただ頭で納得するだけでは不十分なのであって、それが”身体でわかる”段階までいかなけれはいけない。また、分数の概念を”身体でつかみとる”だけではまだ不足で、その体得したものが意識化されなければ分数について“わかる”ところまでいかない。
うっかりすると、リズムはだめでも分数計算はスラスラやれる子供の方が、リズムはできても分数計算は全くできない子供より”進んでいる”ように思いがちですが、私は、実は頭だけでわかったと思いこんでいる場合の方がそうでない場合よりも、困難な問題をかかえていると思います。
二枚の煎餅を三人で分けて食べたり、一本の羊羹を四人で分けたり、手拍子を打ったり歌ったり踊ったりする。ビー玉遊びをして、自分のビー玉の個数が相手の個数の半分だということがわかってがっかりしたり……。こうしたすべてのことは、分数という概念の種子を受け入れる土のようなものだと思います。確かに、何本羊羹を分けて食べても、そこから2分の1、3分の2…という概念が出てくるとは限らない。しかし、そのような生きられた体験が豊かにないところに分数の概念が教えこまれたとしたら、それは砂地に落ちた種子のように乾いて転がり、芽を出さないで終るでしょう」(『こんな算数っているのかな』所収、合同出版)
弥永が述べているように、具体的なものと概念との関係は、生きもののように息づいた関係である。子どもはものと概念、ものと記号の間を何度も行ったり来たりしながら、世界を確かめ、世界を少しずつ広げてゆく。そのプロセスは、酒が時間をかけてゆっくりと発酵してゆくさまと似ている。そこでは、十分な時間と様々な偶然性をはらんだプロセスが子どもに真の知恵をもたらす条件である。 弥永はさらに次のように結んでいる。
「さまざな体験に一条の光を当てられ、それらの体験の中から共通した一つのものが照らし出されるとき、一つの概念が抽出される。そのような概念が意識化されたとき、私たちは空を舞う鳥のように、新しい次元からこれまでの体験の一つ一つを見、しかもそれらを遠く超えて新しい地平をみることもできます。しかし、鳥が絶えず地上の草や虫を食べに降りてこなければならないように、抽象的な概念も絶えず具体的な事柄と関連しあわなければ干からびてしまう。分数計算を覚えても、それを実地に使い、初めはぎこちなくても、ついには分数を”意識”しなくても自然にリズムが身につくところまで言って初めて、分数が本当にわかったといえると、私は思うのです」
”実体験の重要性”という言葉で表現すれば簡単だが、”実体験”は重要だが、そんな時間はないと言われそうで、しかも、「結局、結論はどうなるんですか」という言葉さえ、飛んできそうである。皆さんはどのように考えますか。