
- 解剖用のイモリを採取するために県北に行った。水田はいつもより少なかった。かろうじて川の中で必要数が確保できた。ススキも穂を出し始めているのを見ると、秋の気配がせまっているのを感じる。 アカハライモリ 稲穂をだしている ススキ クマシデ クリ …続きを見る








2009年8月20日

2009年8月19日

2009年8月14日

2009年8月12日

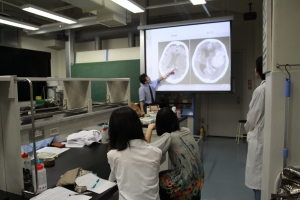
2009年8月11日
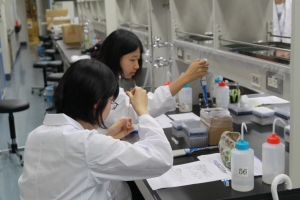
2009年8月 7日

2009年8月 6日

2009年8月 1日


2009年7月31日


2009年7月30日




2009年7月29日



2009年7月28日
