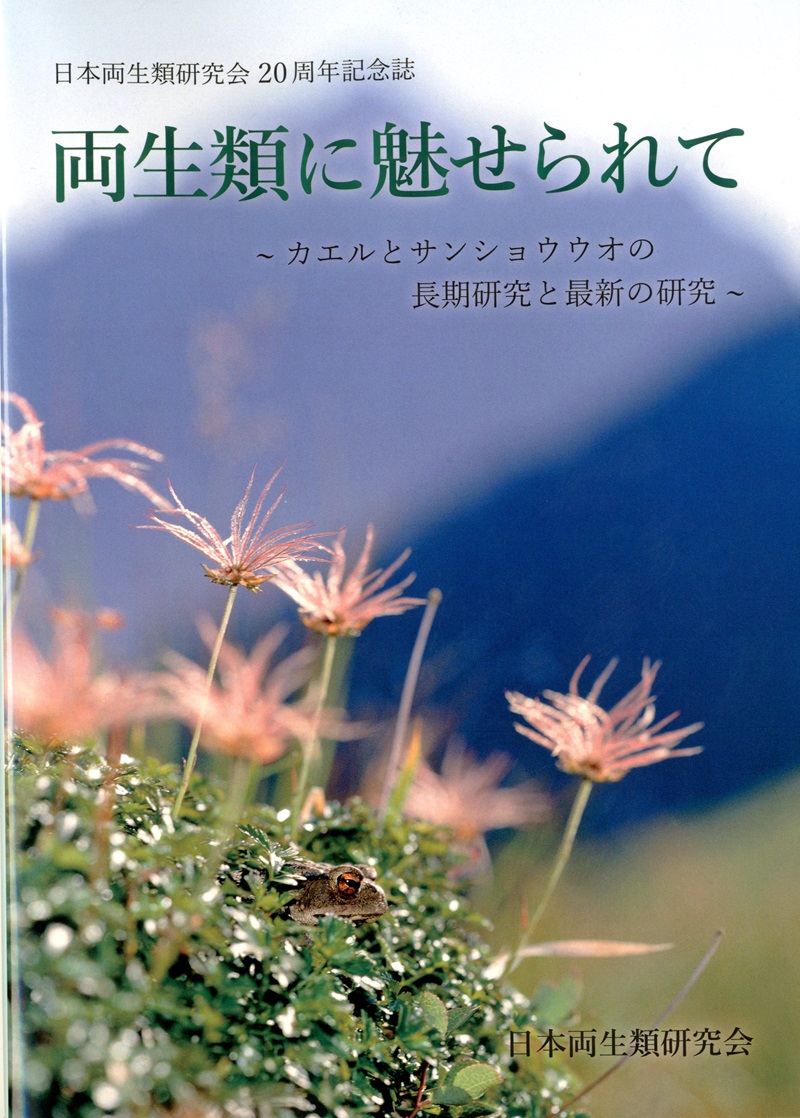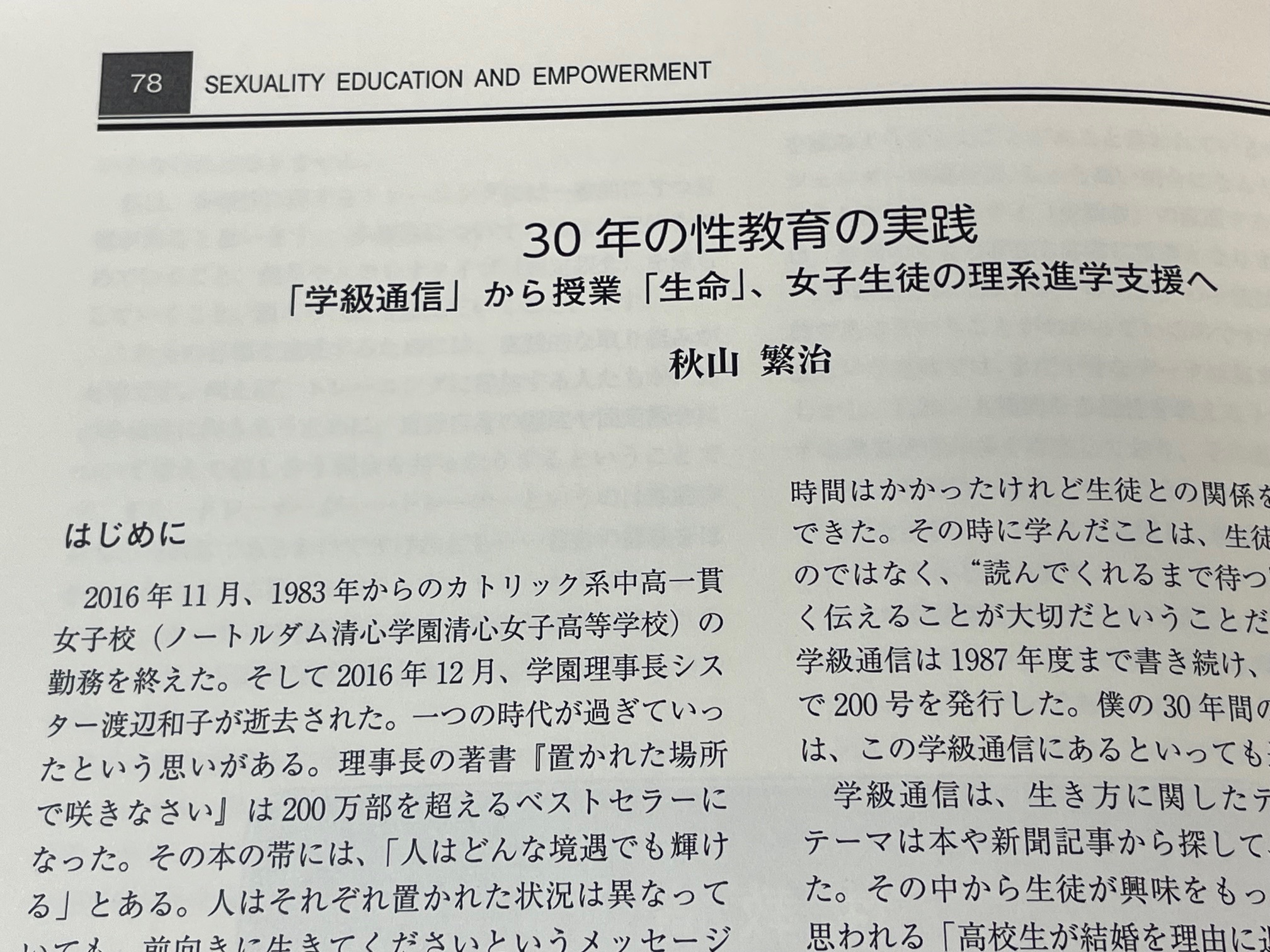
- 授業「生命」 1990 年代は、「リプロダクティブ、ヘルス/ライツ」を提起したカイロ国際人口会議(1994)、女性の地位向上の指針となる「行動綱領」が採択された北京女性会議(1995)、男女共同参画社会基本法の公布(1999)などに象徴されるように、女性の人権に関連した一連の大きな動きがあった。そのような時代に、授業「生命」 (1999)は、ホームルーム活動や総合的な学習の時間での性教育の実践…続きを見る








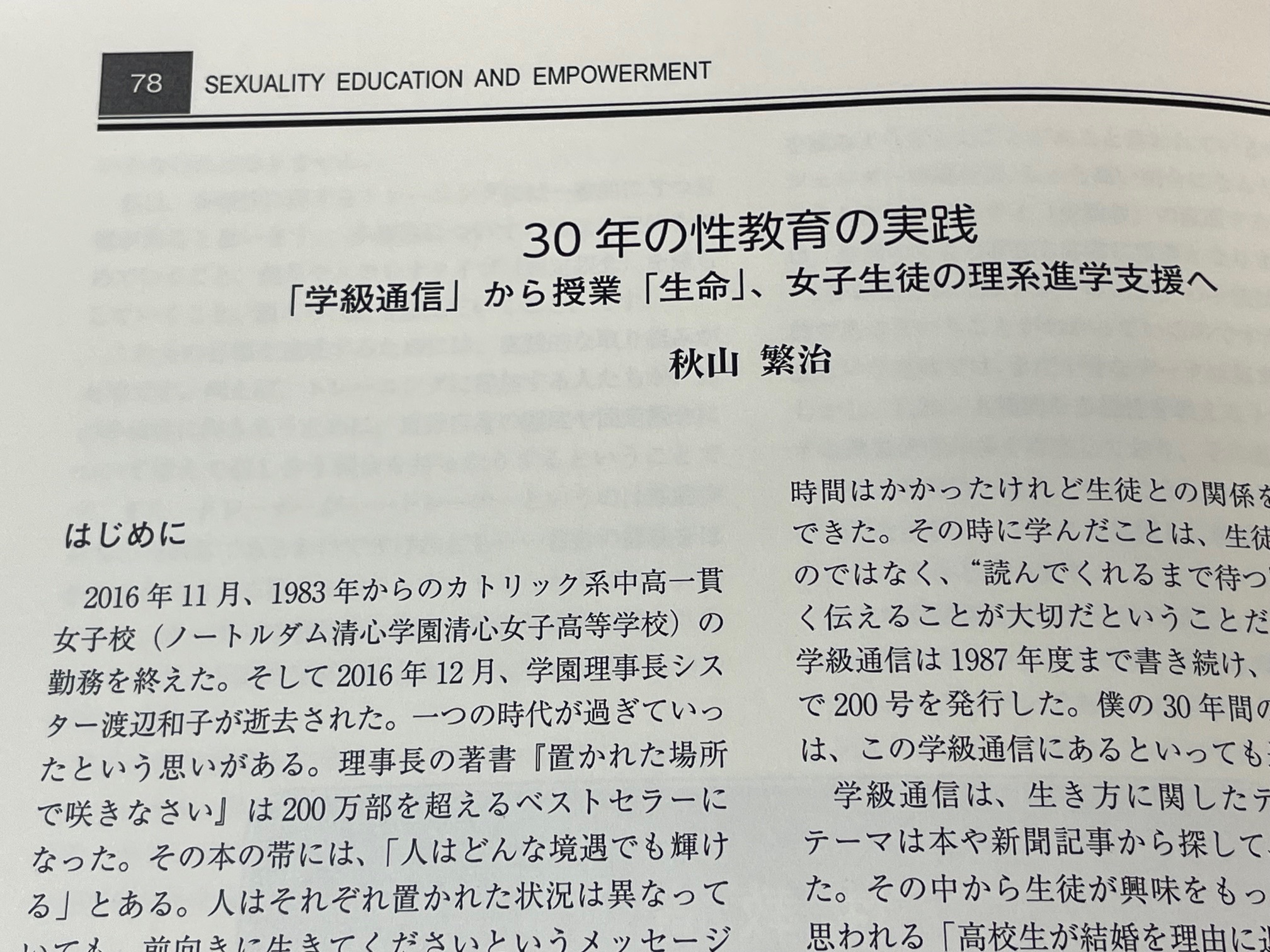
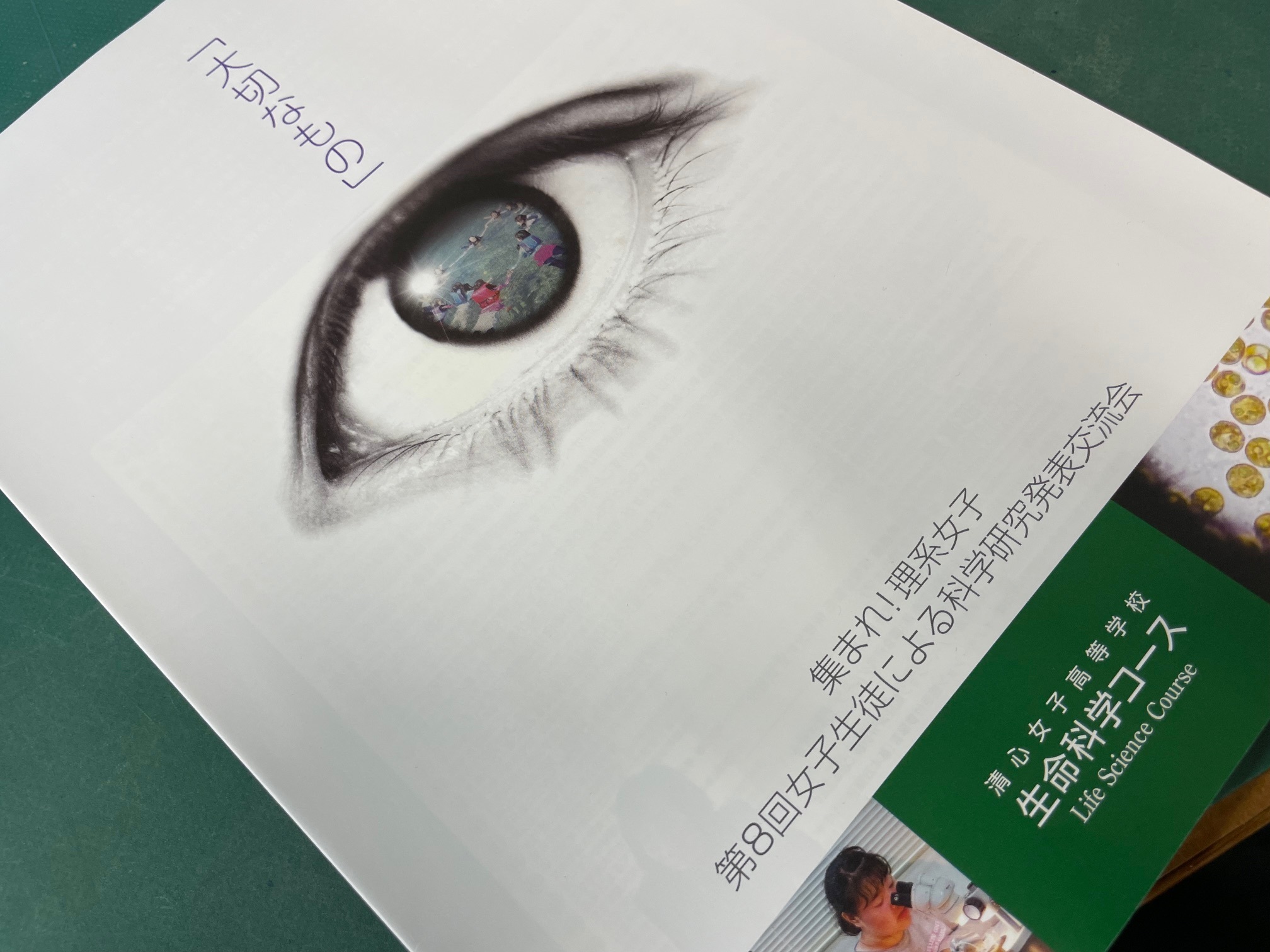
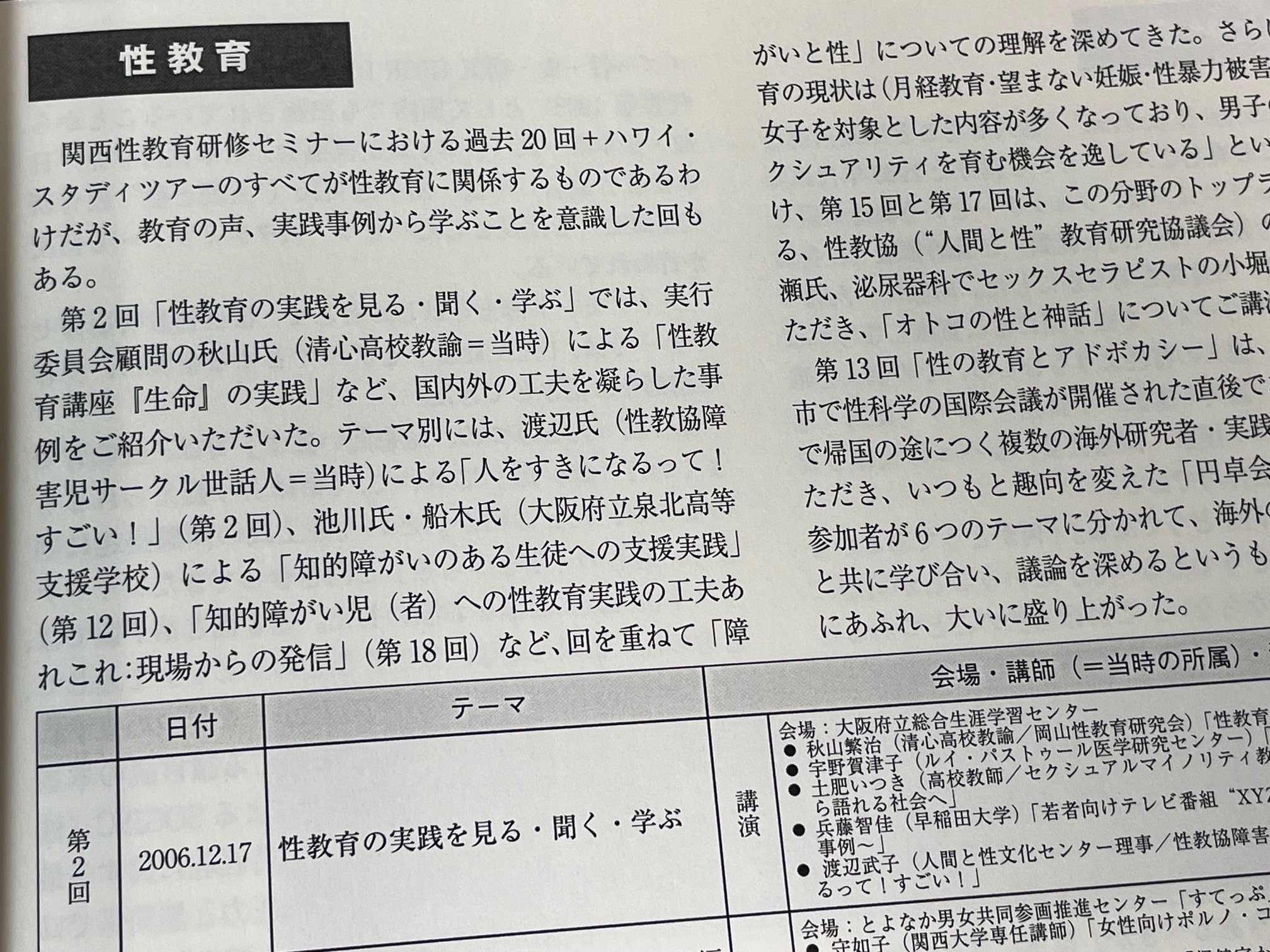
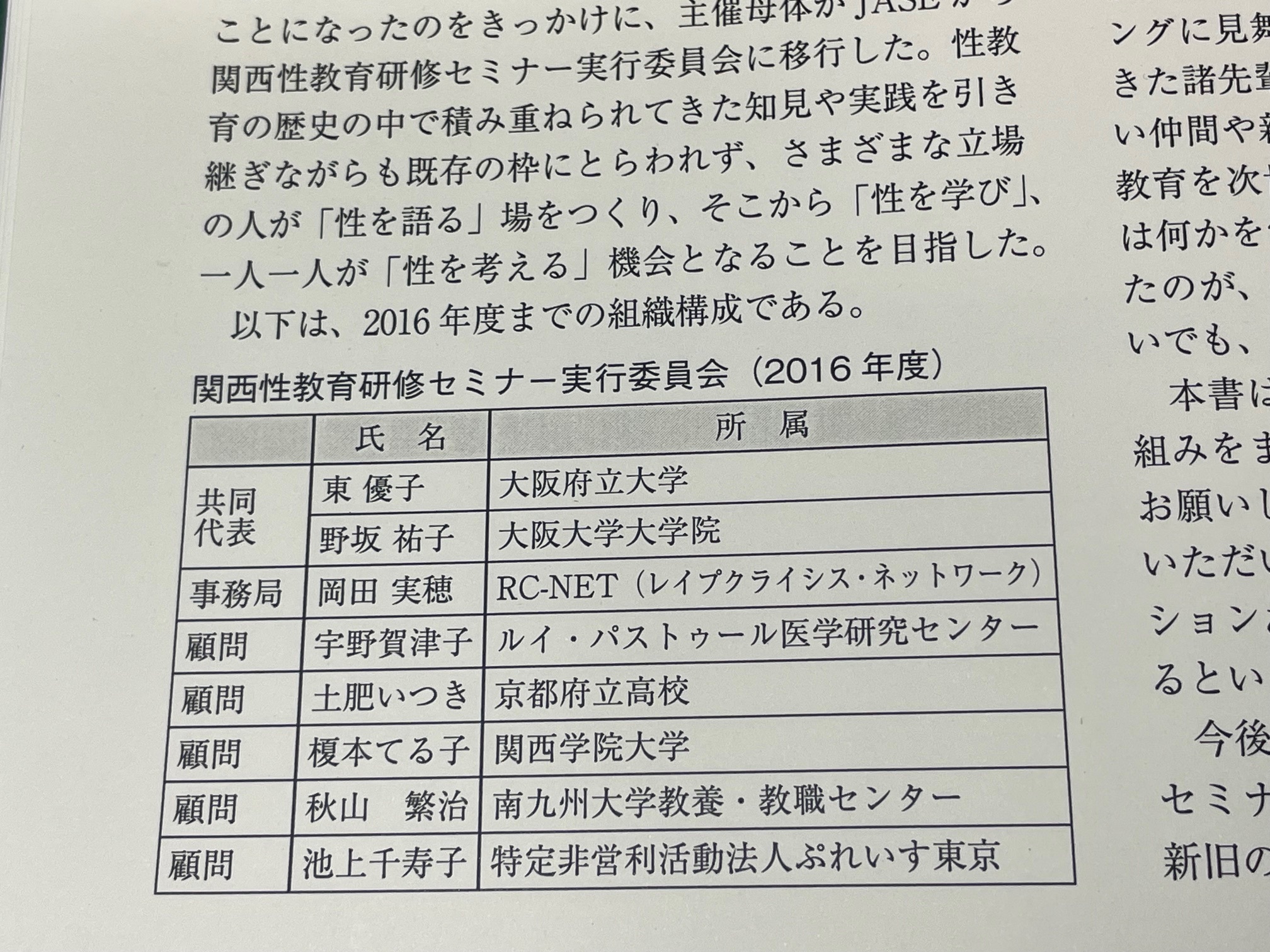
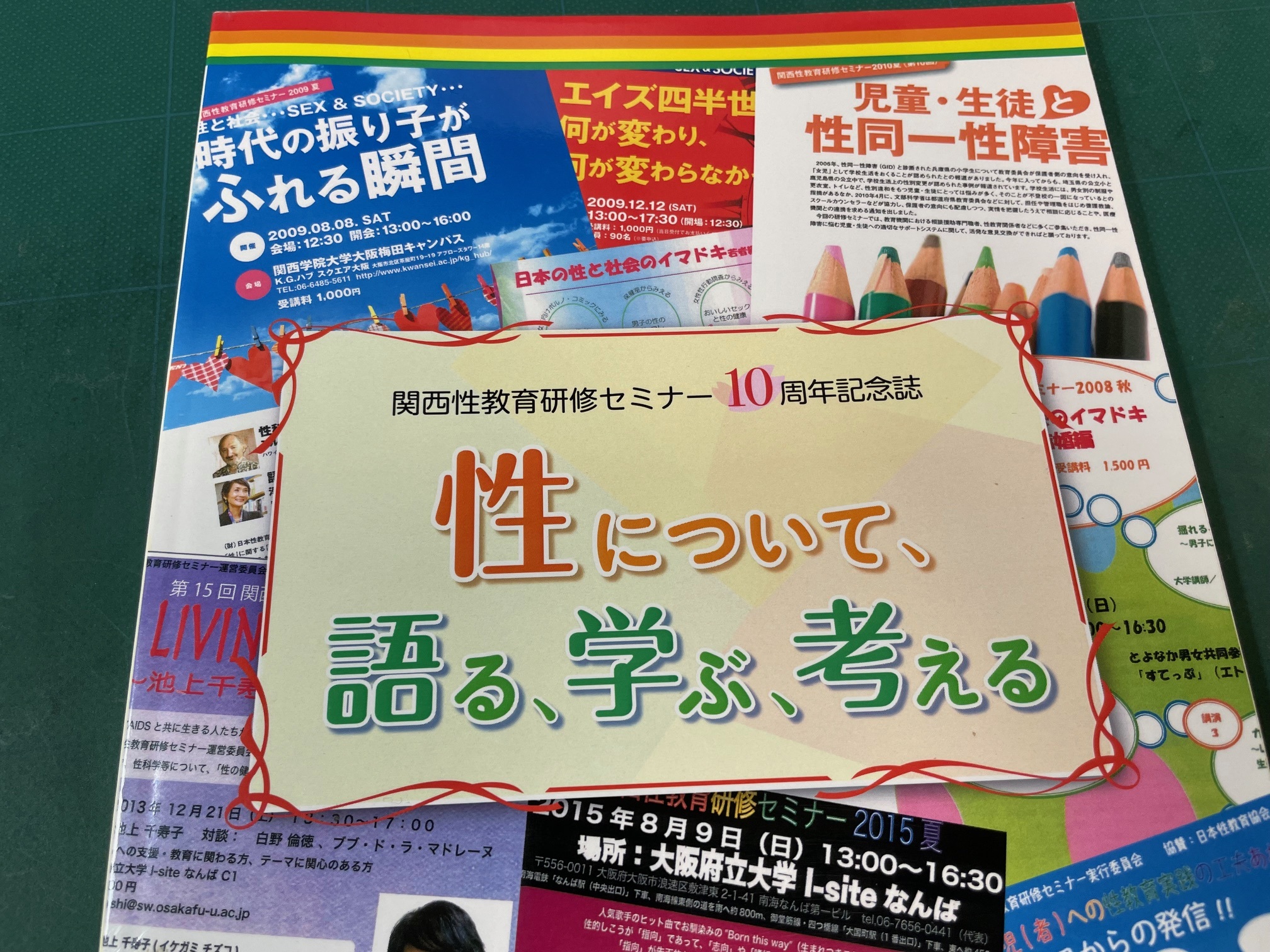
2024年10月14日

2024年10月 9日

2024年10月 5日

2024年10月 4日

2024年9月 9日

2024年9月 7日
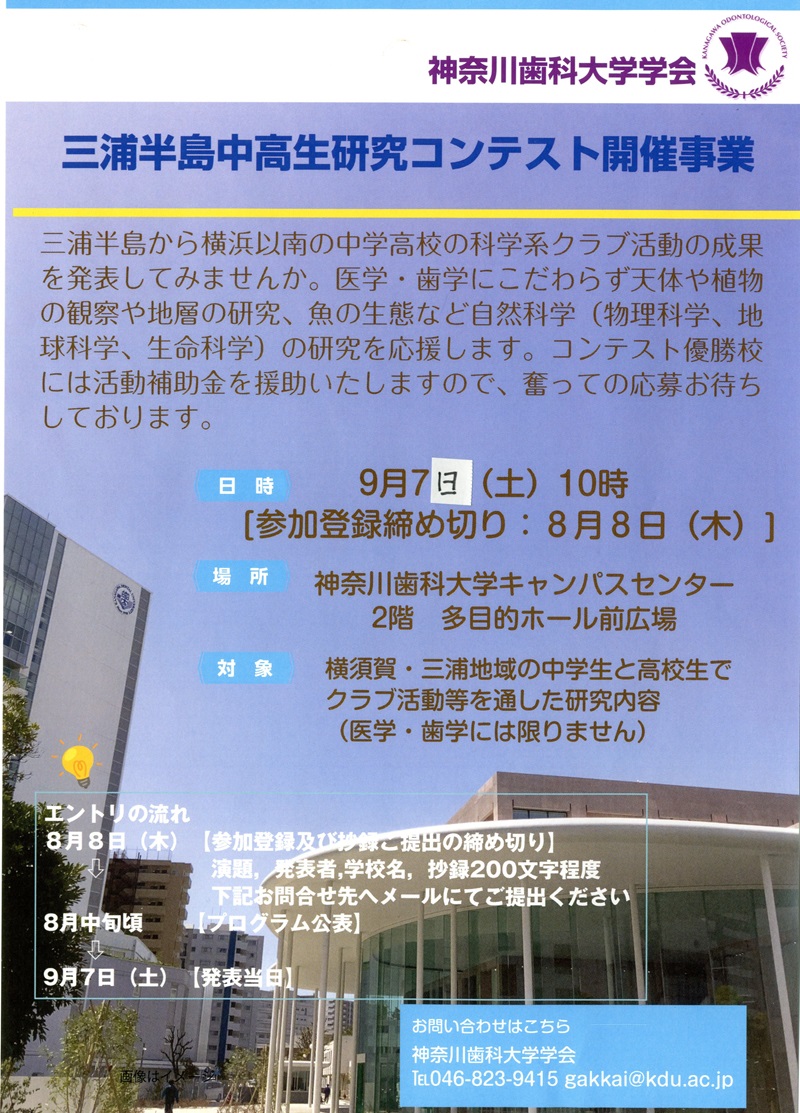
2024年8月25日
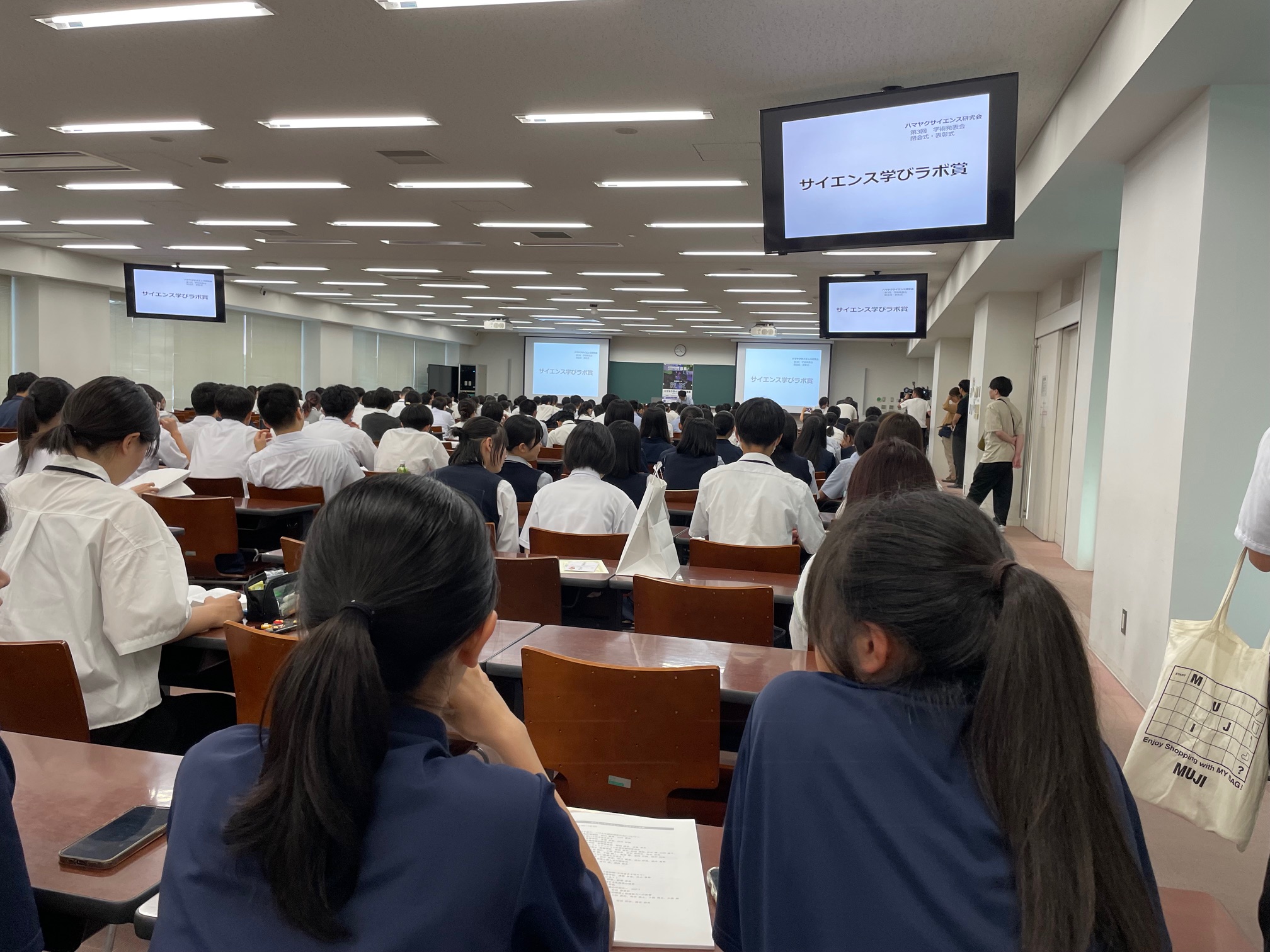
2024年8月 7日

2024年8月 1日
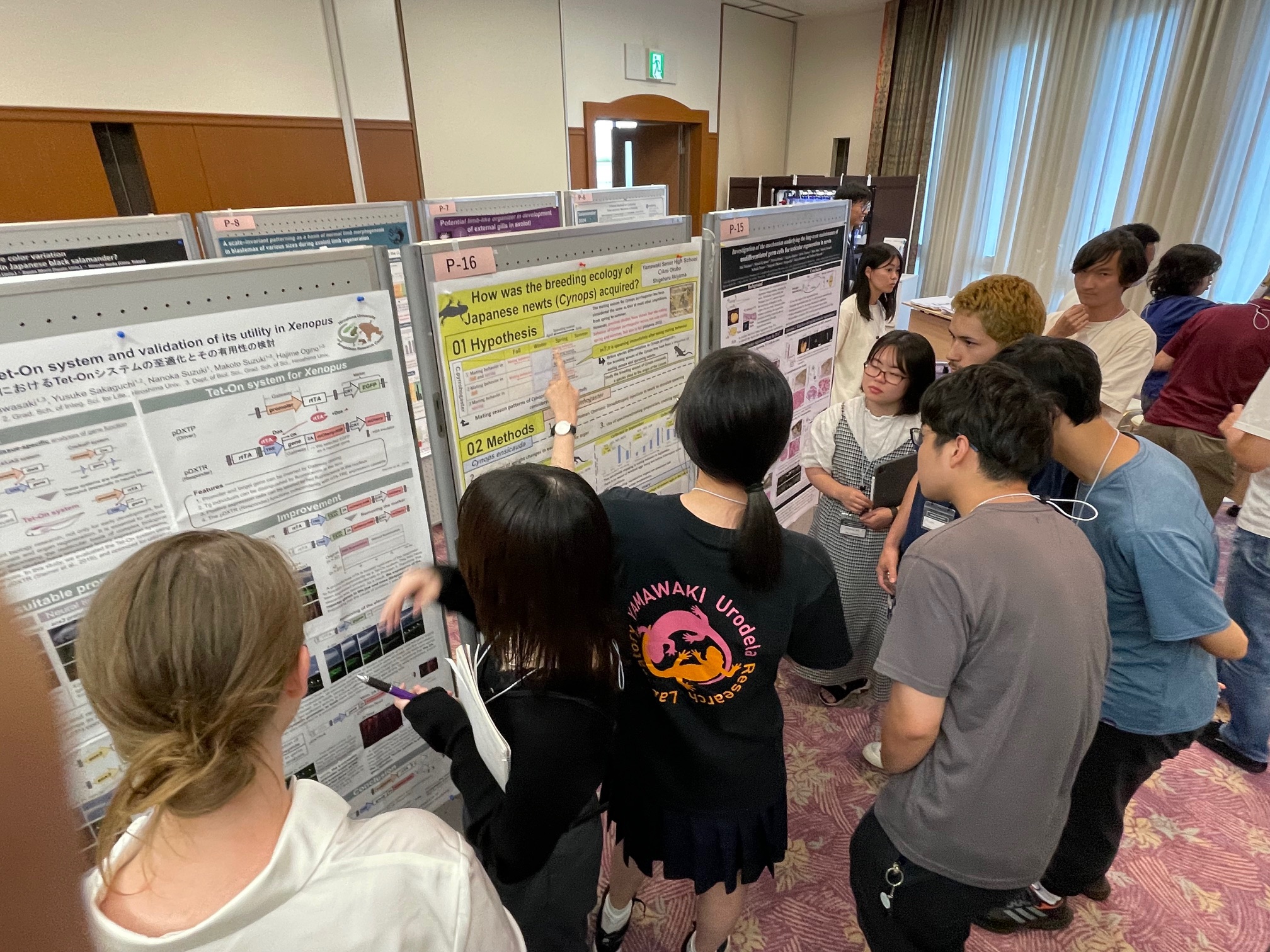
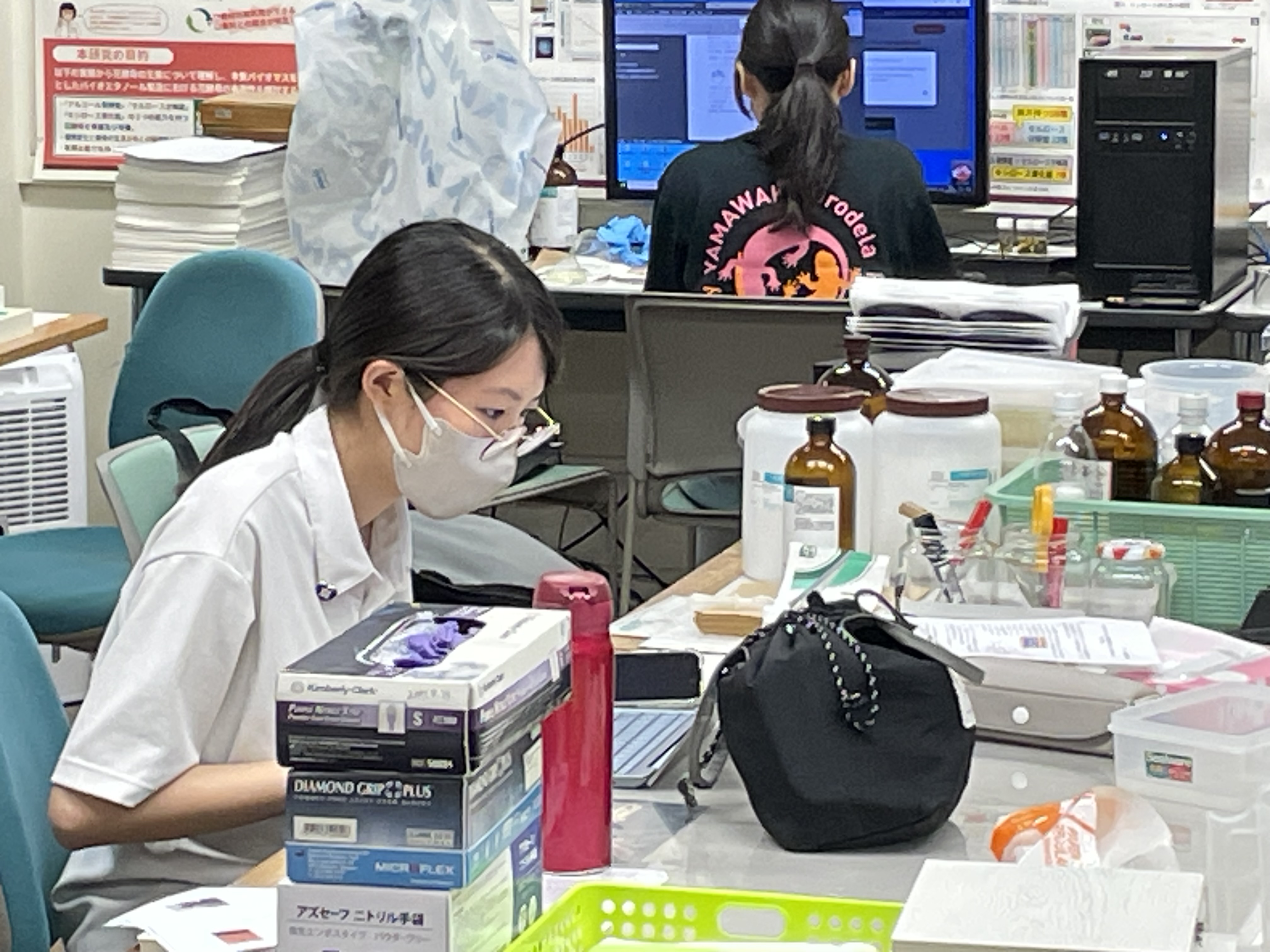
2024年7月23日

2024年7月20日

2024年7月19日