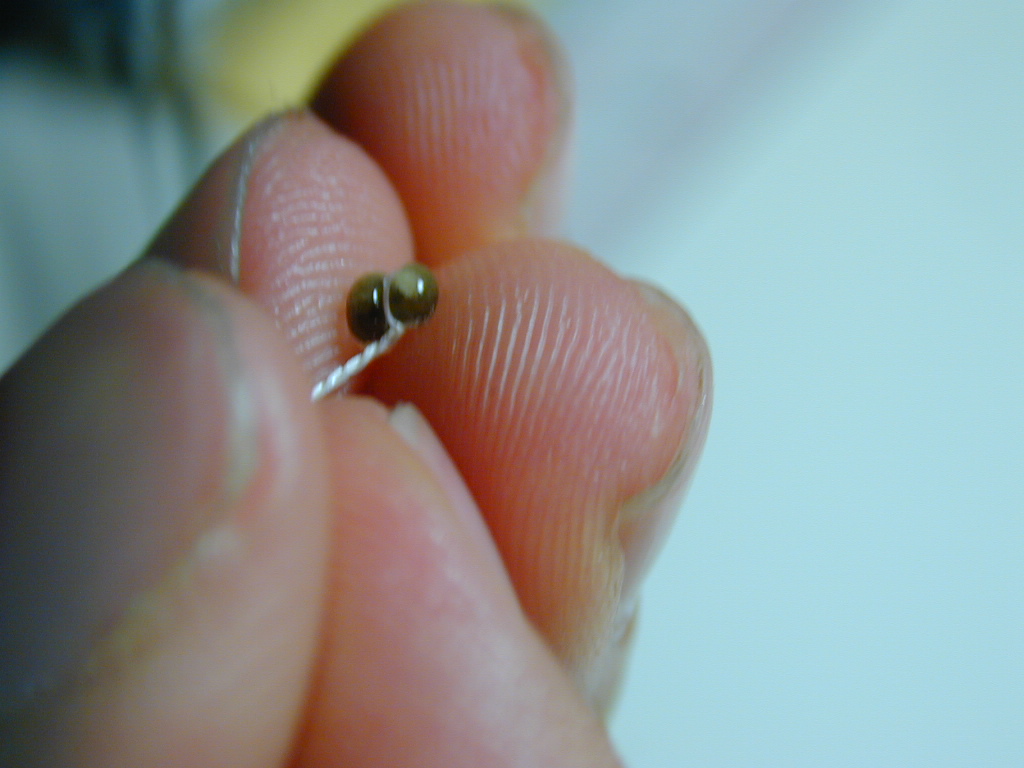- 暖冬と思われるこの時期、ナガレタゴガエルの産卵行動が気になり小雪の舞う県境付近へ入りましたが、ナガレタゴガエルは確認できませんでした(2月中旬に入るのは初めてのことでした~積雪ゼロ)。 水温は4.8℃で、産卵行動の目安となる5.0~6.0℃までは今少しのようです。帰路、県中部の2か所でセトウチサンショウウオ新産地を確認しました。本種の産卵行動はこれからが徐々にピークとなるものと思っております。 …続きを見る








2020年2月17日

2019年12月21日

2019年12月 1日

2019年11月 3日

2019年10月14日

2019年10月13日

2019年10月11日

2019年10月 6日

2019年10月 5日


2019年10月 1日

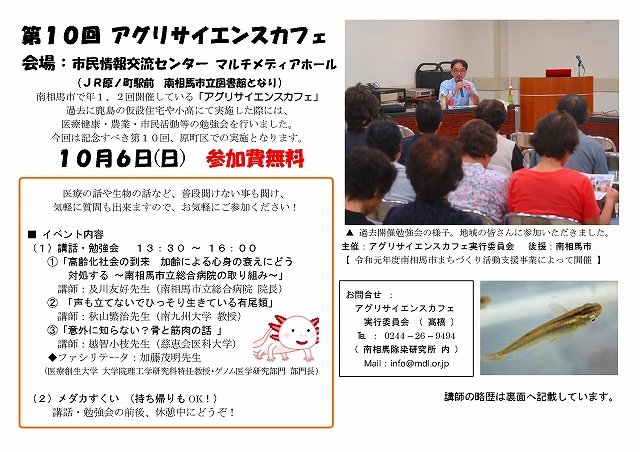
2019年9月23日