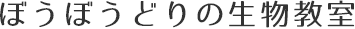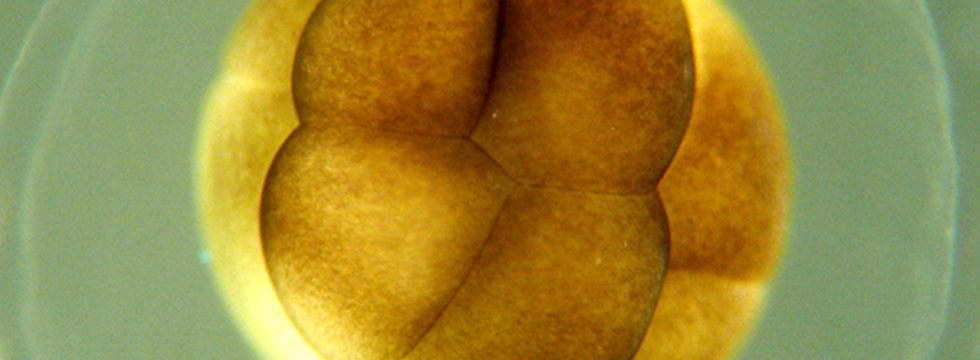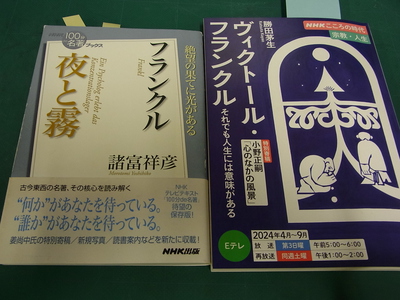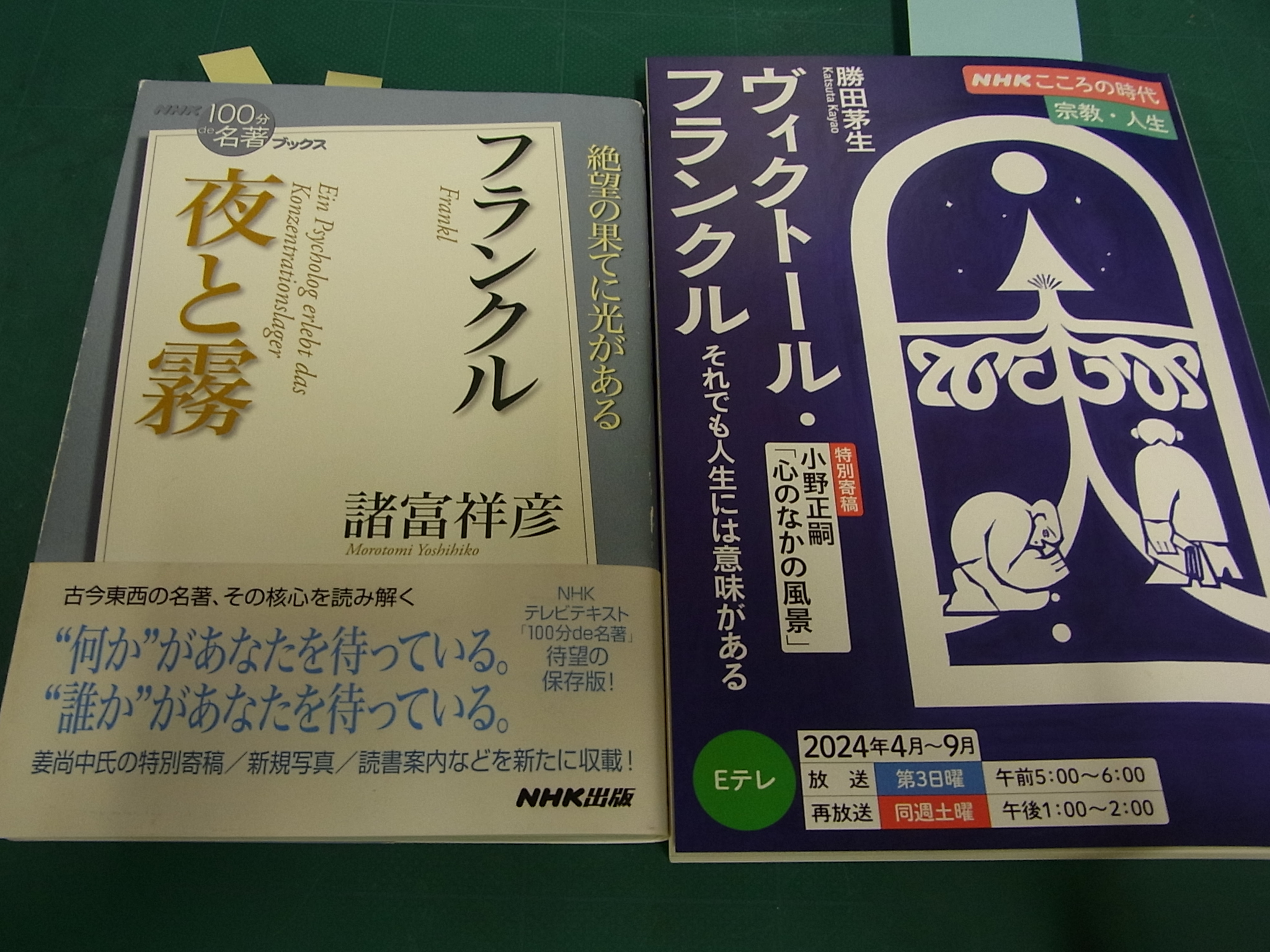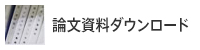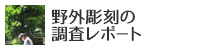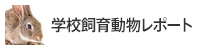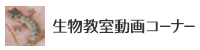いろいろな本を手にして、今までの人生を振り返って考える時間が多くなりました。
以下は、小学校の教科書に掲載されていた「あの坂をのぼれば」と題した短文です。
・・・・・
あの坂をのぼれば、海が見える。
少年は、朝から歩いていた。
草いきれがむっとたちこめる山道である。
顔も背すじも汗にまみれ、休まず歩く息づかいがあらい。
あの坂をのぼれば、海が見える。
それは、幼いころ、添い寝の祖母から、
いつも子守唄のように聞かされたことだった。
うちの裏の、あの山を一つこえれば、
海が見えるんだよ、と。
その、山一つ、という言葉を、少年は正直に
そのまま受けとめていたのだが、それはどうやら、
しごく大ざっぱな言葉のあやだったらしい。
現に、今こうして、峠を二つ三つとこえても、
まだ海は見えてこないのだから。
それでも少年は、呪文のように心に唱えて、のぼってゆく。
あの坂をのぼれば、海が見える。
のぼりきるまで、あと数歩。
半ばかけだすようにして、少年はその頂に立つ。
しかし、見下ろす行く手は、またも波のように、
くだってのぼって、その先の見えない、
長い長い山道だった。
少年は、がくがくする足をふみしめて、
もう一度気力を奮い起こす。
あの坂をのぼれば、海が見える。
少年は、今、どうしても海を見たいのだった。
細かく言えばきりもないが、やりたくてやれないことの
数々の重荷が背に積もり積もったとき、
少年は、磁石が北を指すように、
まっすぐに海を思ったのである。
自分の足で、海を見てこよう。
山一つこえたら、本当に海があるのを確かめてこよう、と。
あの坂をのぼれば、海が見える。
しかし、まだ海は見えなかった。
はうようにしてのぼってきたこの坂の行く手も、
やはり今までと同じ、果てしない上がり下りの
くり返しだったのである。
もう、やめよう。
急に、道ばたに座りこんで、
少年はうめくようにそう思った。
こんなにつらい思いをして、
いったいなんの得があるのか。
この先、山をいくつこえたところで、
本当に海へ出られるのかどうか、わかったものじゃない。
額ににじみ出る汗をそのままに、草の上に座って、
通りぬける山風にふかれていると、
なにもかも、どうでもよくなってくる。
じわじわと、疲労が胸につきあげてきた。
日は次第に高くなる。
これから帰る道のりの長さを思って、
重いため息をついたとき、少年はふと、
生きものの声を耳にしたと思った。
声は上から来る。
ふりあおぐと、すぐ頭上を、光が走った。
翼の長い、真っ白い大きな鳥が一羽、
ゆっくりと羽ばたいて、先導するように次の峠を
こえてゆく。
あれは、海鳥だ!
少年はとっさに立ち上がった。
海鳥がいる。
海が近いのにちがいない。
そういえば、あの坂の上の空の色は、
確かに海へと続くあさぎ色だ。
今度こそ、海に着けるのか。
それでも、ややためらって、行く手を見はるかす
少年の目の前を、ちょうのようにひらひらと、
白いものが舞い落ちる。
てのひらをすぼめて受けとめると、それは、
雪のようなひとひらの羽毛だった。
あの鳥の、おくりものだ。
ただ一片の羽根だけれど、それはたちまち少年の心に、
白い大きな翼となって羽ばたいた。
あの坂をのぼれば、海が見える。
少年はもう一度、力をこめてつぶやく。
しかし、そうでなくともよかった。
今はたとえ、このあと三つの坂、
四つの坂をこえることになろうとも、
必ず海に行き着くことができる、
行き着いてみせる。
白い小さな羽根をてのひらにしっかりとくるんで、
ゆっくりと坂をのぼってゆく少年の耳に
あるいは心の奥にか
かすかなしおざいのひびきが聞こえ始めていた。