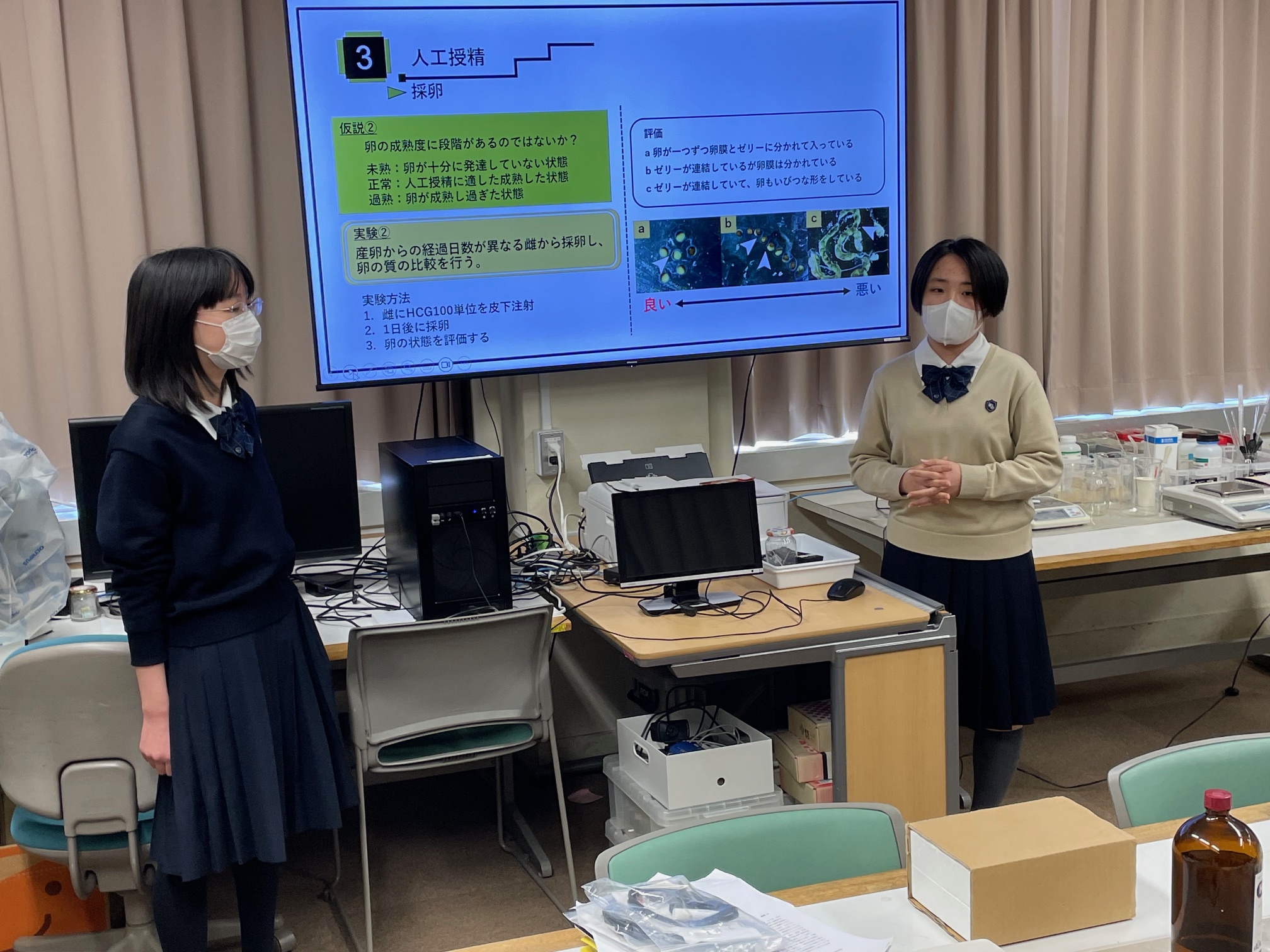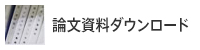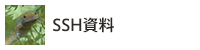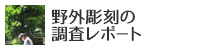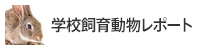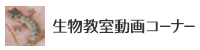90代の高齢女性が、初老の男性に担がれて救急外来を受診されました。主訴は「両下肢が赤く腫れた」ということでしたが、それより、救急のスタッフたちが驚かされたのは彼女の全身が放つ異臭だったようです。
初老の男性は同居する長男でしたが、その長男によると、彼女は4年前から歩くことができなくなり、その頃から風呂にも入っていないとのこと。病院を受診することも、福祉を利用することもなく、ずっと家のなかでフケと垢にまみれて生きていたようです。
救急のナースたちは手慣れたもので、早速、彼女の体を丹念に洗い流していました。蜂窩織炎との診断により(感染症医である)私が呼ばれたときには、すでにサッパリとした表情で病棟のベッドに寝かされていたのでした。
私が診察をはじめると、長男は困惑した表情で、私の指先を追いかけていました。口腔内は不潔で、舌圧子で拭うと灰汁(あく)のようなものが掻きだされてきます。「入れ歯の掃除をさせてくれないんですよ」と長男が申し訳なさそうに言いました。
胸腹部に異常所見なし。体幹には引っ掻き傷が散在していますが、疥癬ではなさそうです。一方、両側の腰部には大きな褥瘡がありました。黒く変色した壊死組織が付着しており、これは早めに削った方がよさそうです。
「ご自宅ではベッドでしたか?」と私が聞くと、長男は「いえ、ムシロを敷いて、その上で寝ていました」と答えました。驚いて「マットはなくて、固い床の上ですか?」と問いただすと、「ムシロでしか寝てくれないのです。昔から・・・」と弁解するように長男は言いました。
その初老男性の目を見つめ返しながら、私は、長野県で後期研修医となったばかりのときの失敗を思い出していました。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
救急外来に運び込まれた80代の女性は、やはり猛烈な異臭を放っていました。オムツが重く垂れさがり、便汁が染み出しています。開けてみると大量の糞塊があふれ出てきました。息子と2人暮らしでしたが、あらゆる介護を放棄しているかのように私には見えました。食べ物をもっていっても口にしなくなったとのことで、ようやく息子は救急車を呼ぶ気になったようでした。
救急搬送時から担当した私は、この高齢女性の在宅調整に全力をあげました。介護保険を導入し、村の保健師と連携し、ケアマネと何度も打ち合わせ、「これなら安心して息子と暮らしてゆけるだろう」と納得できるケアプランを練り上げたのです。
そして、退院前日、ケアマネを交えて最後のカンファレンスをもちました。1週間の介護スケジュールを再確認したあと、私は息子に言いました。
「あなたの負担は最小限になったと思います。ただ、夕方のオムツ交換だけはあなたの役割です。よろしいですね。
しかし、息子の返答は三年目の医者に過ぎない私にはとても理解できないものだったのです。
「そんなの知るか! クソまみれで死ぬなら死ねばいい」
私が患者さんのご家族にキレたのは、このときが最初であり最後です。正気を失った私は息子に暴言を吐き、そしてカンファレンスは崩壊したのです。
のちに、この親子が暮らしている村の診療所長から諭されました。
「医療や福祉の手法をひけらかしても、やっぱり介護の主役は家族なんですよ。先生のやり方では、家族が取り残されていましたね。息子さんの気持ちを追い込んでいることに、もう少し早く気がついてほしかったです」
息子の介護力のなさを私がほのめかすと、診療所長は少し厳しい口調で言いました。
「息子さんは何年も介護をつづけていました。誰の手も借りずに、食事をつくり、体をぬぐい、オムツだって替えていたんです。なぜ、できていないと言えるんですか? 親子の関係とは単純なものではないですよ。そこに先生が敬意をもてれば、流れは変わっていたでしょうね」
私は黙り込むしかありませんでした。
身体は、愛情に比べれば、はかないものです。だから、親たちはしばしば子どものために、身体を犠牲にします。むしろ、身体をそのように処することで子どもへの愛情を表現しようとすることもあるのです。年老いた親が介護に抵抗するとき、子はどのように振る舞えばよいのでしょうか? 思いを馳せることができていなかったのです。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
沖縄県の病院で、ふたたび高齢女性をはさんで、白髪交じりの長男と向かい合いながら、そんなことをふと私は思い出していました。
さて、問題の下腿へと診察をすすめてゆきます。水疱が多発しており、そのほとんどが破れ、潰瘍を形成していました。残存する水疱は緊満しています。おそらく類天疱瘡を強く引っ掻いて破ったものと思われました。
長男が言い訳するように、「掻くんですよ。やめろって言ったんですけどね」と言いました。低温熱傷ではないことを確認するつもりで、「電気マットをあてたり、ヒーターのそばに足を置いたりしませんでした?」と私は聞きました。
すると、質問の意図を勘違いしたのか長男は「あっためた方がいいとも言ったんですよ。でも、嫌がるんですよ」と言い訳を重ねていました。そして、「破れたところにはね。アロエを貼っていたんですが、あんまり効かなかったですね」と。病院に母親を連れてきて半日。多くの視線にさらされ、たくさんの質問を受け、指摘をされ、十分に彼は傷ついているに違いありません。その場の重たい空気を振り払うように、私は笑顔で言いました。もう、あの失敗は繰り返したくはないのです。
「ほんとにご苦労さまでした。いろいろと頑張って来られましたね。でも、良いタイミングで病院に連れてきていただきました。しばらく私たちに任せてください。今後のことも一緒に考えてゆきましょう。きっとこれからも幸せに生活できるようお手伝いができると思います」
長男はへたへたと椅子に座り込み、そして、小さく「ありがとうございます」と呟いていました
出典:高山義浩著『地域医療と暮らしのゆくえ』