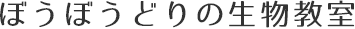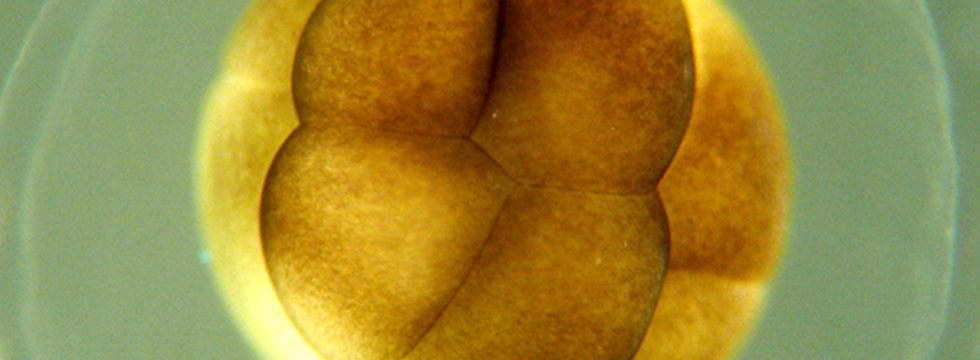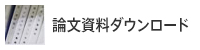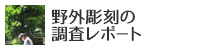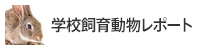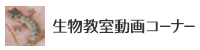今回の医学部の入試が問題になるずいぶん前に、京都大学で女子の受験者を配慮した入試が行われていたようです。以下は、森嶋通夫・著『智にはたらけば角が立つ』(朝日新聞社・1999)p94-p96からの抜粋です。
新制の入学試験には私は関係なかった。その代わり、合否決定の会議には出席した。合否の決定は通常、次のようにして機械的に決定されるのだが、その時は横槍が入った。
通常の手続きとはこうである。まず事務部が、受験生を各科目の点数の総計の順に並べた覧表をつくる。本人の姓名はもちろん、受験番号も伏せられている。次に定員数(300名)の前後の受験者の総計点に注目するよう学部長が注意をし、総計点が大幅に落ちる前までを合格とする。295人目から6人目の間にはっきりした差が見られるなら295人までを合格とする。304人までは踵を接する状態で並んでおり、305人との間に初めて明瞭な差が認められるならば、定員を超えてはいるが304人までを合格とする。
その日もこういう方式で合格者は簡単に決まった。が、その直後に間髪を入れずに青山先生の横槍が入ったのである。
「これらの合格者のなかに女子学生はおりますか」
事務長は「いない」と言った。一覧表には、余分となってしまうかなり多くの次点者の点数も書かれていたが、それらのなかにも女子学生はいないと事務長が言い足した。
「女子学生だけの点数を選り抜いて持ってきてください」
先生の追及は厳しかった。事務長は事務室に下りていって、14、15人の点数表をつくり、
それを読み上げた。それは惨憺たるものであった。先生はどこの高校の卒業生かわかりますかと事務長に聞き、事務長は学校名を読み上げた。私は「ひょっとしたら、先生の知人の女子学生が受験しているのでないか」といぶかった。私同様に思っていた人も大勢いたかもしれない。
先生は「わかりました」と言い、それからなぜ女子学生を入学させねばならないかを説明し始めた。
「将来の社会は男女同権の社会である。大学はそういう社会をつくっていく義務がある。それだのに、われわれが男女に差をつけずに入学者を決定すれば、いつまでたっても女子学生は入学しない。つまり大学自身が男女同権の社会をつくるのを妨害しているのです。男の子は思う存分、受験勉強ができる。しかし女の子は夕食前には、お母さんの炊事を手伝わなければならない。これでは試験の結果に差ができるのは当然です。男女を平等にするためには、まず男女を不平等に扱わねばなりません」
当時にはまだ逆差別という言葉はなかったが、「まず逆差別をしろ」という先生のロジックは教授会ですぐ受け入れられた。しかし何人合格させるかについては、指令も基準も枠もないから、皆がそれぞれに考えている人数はなかなか収斂しなかった。
結局、二人合格させようということで合意が成立したが、彼らを一般の合格者と同じに見なすことは、外部から万一文句が出た時、言い訳に困るからということになって、彼らを「女子特別入学者」とすることにした。こうして京大は女子教育に門戸を開いた。青山先生の勝利であり、功績である。