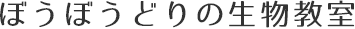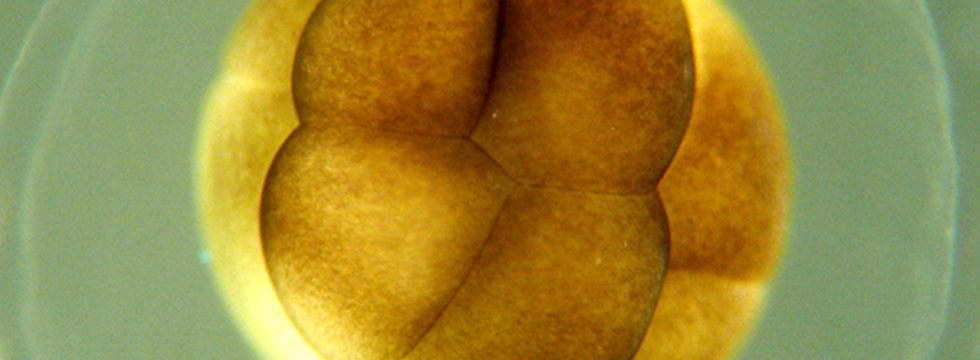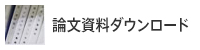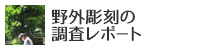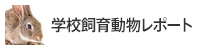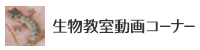「厳しく叱って育てる教育が大切なのに、今の社会ではその重要性が理解されていない」と嘆く教員や保護者がおられますが、本当でしょうか。教育についての心理学者アドラーの意見に少し耳をかたむけてみてはどうでしょうか。以下は、NHK「100分de名著・人生の意味の心理学(アドラー)」からの抜粋です。
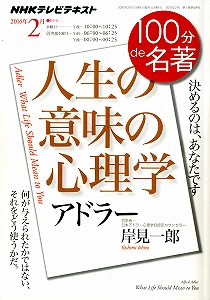
アドラーが教師に寄せる信頼は大きく、「教師は子どもたちの心を形作り、人類の未来は教師の手に振られている」(『子どもの教育』)、とまでいっています。他方、アドラーが親に向ける日は厳しく、教師は、家庭における親の誤った教育の結果である子どもを学校で引き受け、家庭での教育の誤りを教師が補わなければならないといっています。親は「再教育」が必要だともアドラーはいっていますが、『人生の意味の心理学』においては、「教師は、母親と同様、人類の未来の守護者であり、教師がなしうる仕事は計り知れない」といっているように、親の協力も子どもの教育にとっては必須のものです。
アドラーの教育論の基本は「勇気づけ」にあります。親や教師は、子どもが共同体感覚を持ち、対人関係の中に入っていく勇気を持てるように援助しなければなりません。
教育の世界では、伝統的に「叱ること」と「ほめること」が重視されてきました。しかし、アドラーはそのどちらも認めていません。これは一体どういうことなのか考えてみなければなりません。叱るという行為は、上下の対人関係を前提としています。このテキストの序文で、アドラーは「あらゆる対人関係は『縦』ではなく『横』の関係にあり、人と人とは対等である」と考えた!という話をしましたが、親と子の関係が対等だと考えるならば、親には子どもを叱ることはできないはずです。叱らないのは放任ではないかと批判する人もありますが、必要があれば責任を取ることを子どもは学ばなければなりません。
失敗の場合は、まず、可能な限りの原状回復をします。次に、もしも失敗によって感情的に傷ついた人がいれば謝罪することが必要です。さらに、今後同じ失敗をしないための話し合いをすればいいのです。叱る必要などまったくありません。
また、叱られて育つと、人の顔色ばかり窺うスケールの小さな人間になってしまいます。人間というのは本来、ごつごつした尖った部分をそれぞれが持っています。この尖った部分が個性です。それを短所や欠点と見なし、矯正しょうとすると、また、時には何も起こらないうちから叱って子どもの失敗を未然に防ぐようなことばかりをしていると、尖った部分を取り除かれることで、たしかにいい子になるかもしれませんが、自分で創意工夫をして何かをやろうという子どもには育たなくなります。
アドラーは、叱ることだけでなくほめることも否定しました。ほめられて育った子どもは、何かをしようとする時に、承認されることを期待するようになります。誰も見ていなければ適切な行動をしなくなることは大きな問題です。
さらに、より重要なこととしては、ほめることも、叱ることと同様に、子どもを対等な存在と見なしていないということです。ほめるという行為も上下の関係が前提となっています。例えば母親は子どもに買い物を頼んで、子どもがそれをちゃんとできたら、「偉かったわね」とはめるでしょう。しかし、妻が夫に買い物を頼み、夫がそれをこなしたときに、妻は夫に「偉かったわね」とは決していわないでしょう。ほめるというのは、能力のある人が能力のない人に対して、上から下す評価の言葉なのです。ほめることができるとすれば、その人の、他者との対人関係の構えが上下関係であるということなのです。子どもでも大人でも、対人関係の下に置かれることを好む人はいません。