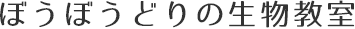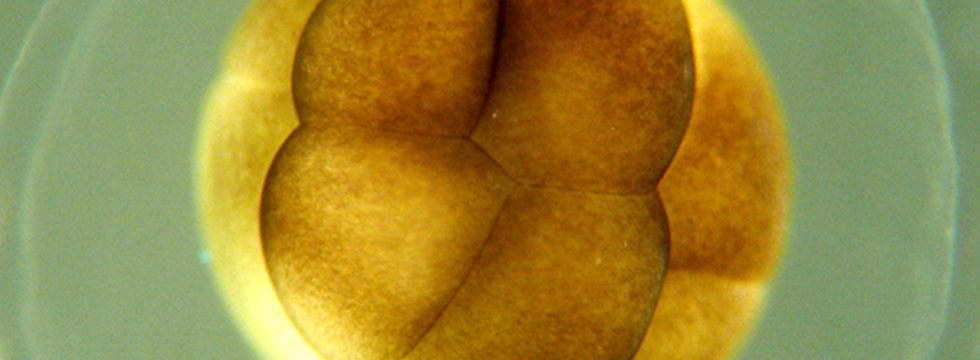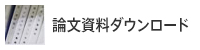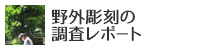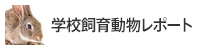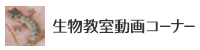湯川秀樹にとって、母親の存在が大きく、また彼自身が書いた自伝でも詳細に記載されていることがわかる。以下は、湯川秀樹『旅人(湯川秀樹自伝)』角川文庫p126-129より抜粋。
子にとって重要な問題は、いつも母にとっても重要なのだ。しかも、秀樹としう子は、比較的無口なところといい、物静かなところといい、この母親によく似た子だ。いや、静かな中にも強奴なものを一筋、はっきりとつかんでいるらしい点も、共通している。
私の質問は、すでに妻に打撃を与えたのだろうか?
服を着終えると、琢治は再び書斎に入って、持って出るはずのかばんの内容を調べた。また立ち上ると、
「すぐ、お出かけですか?」
強い妻の言葉が、しっかりした調子で背に来た。
「さきほどのお話、どういうことでしょうか?」
琢治はふり返った。それから静かな微笑をうかべた。それは長い間、苦楽を分け合って来た妻に対するいたわりの微笑のようでもあった。
「また、夜でも話をする」
「はい」
「考えて置いてくれ」
「はい」
妻は、大学へ出かける夫を、玄関まで送って出た。靴をはき終えた夫に、かばんを手渡しながら、不意に言った。
「秀樹も、もちろん大学までいくことと思います」
「............」
「あの子にだけ、どうしてそんなことをお考えになったのですかP」
「ふむ」
「目立たない子も、あるものです。目立つ子や、才気走った子が、すぐれた仕事をする人間になるというわけでは、御座いますまい。かえって目立たないような人間が......」
琢治は、毅然とした妻の声を胸に刻んだ。彼女の生れ、彼女の育ちを思わせる声である。その上に、母親としての強さと、誇りがある。いつもの無口な、ひかえ目な女ではなかった。言葉を切るたびにきりりとひきしまる口は、すぐ次の、自信ある言葉を用意するかのようだ。
「......それに、どの子にも同じようにしてやりたいと存じます。不公平なことは出来ません」
私だって、子供たちに不公平なことはしたくない。
と、琢治は思った。
「よし、お前の意見は分った。また、夜にでも話そう」
そう言って、家を出た。
妻の意見も、筋が通っている、と彼は思うのだ。それはそれなりに立派である。が、自分の考えだって、間違っているわけではない。
子供を、子供自身にとって一番ふさわしい道に進ましてやることが、親の義務ではないか。
なるほど、小川家では、子供たちをみな学者にするように、知らず知らず仕向けていた。なんの疑間もなく、自分たちは子供を学者にするつもりでおり、子供たちも多分、そう思って日を重ねて来ただろう。しかし今、子供たちは順々に、少年期から青年期に入って行こうとしている。次第に個性を目ざめさせている。一律に同じ方向にのばすことが果して正しいかどうか。親にそれだけの権利があるかどうか。
琢治が三男秀樹を専門学校にやろうかと思い出してから、もうしばらくの日が経っている。学校でも、長男や次男ほどには目立たない子だ。だから彼には、彼にふさわしい道を歩かせようかと考えたまでのことだ。決して不平等というわけではない。五人の男の子に、それぞれみんなちがう道を歩かせたところで、それが五人のそれぞれにふさわしい道であれば、かえって公平といえるだろう。好む者も好まない者も、それにふさわしい者もふさわしくない者も、みんな一つの道を歩かせるとしたら、これこそ悪平等ではないか。
琢治はその日、子供たちのことを考える時間が、いつもより多いのに気づいた。
いや、次の日も、また次の日も、以前に比べたら子供たちのことを余計に考えている。子供たちが、それぞれの岐路に近づいていることが、手にとるように分る。彼らは彼らの人生にとって、いわば決定的な年代に踏みこもうとしているのだ。それを放り出して置いては、たとえ彼らの知恵と判断力をいかに高く評価するとしても、親としては怠慢のそしりは免かれまい。