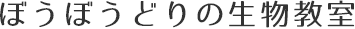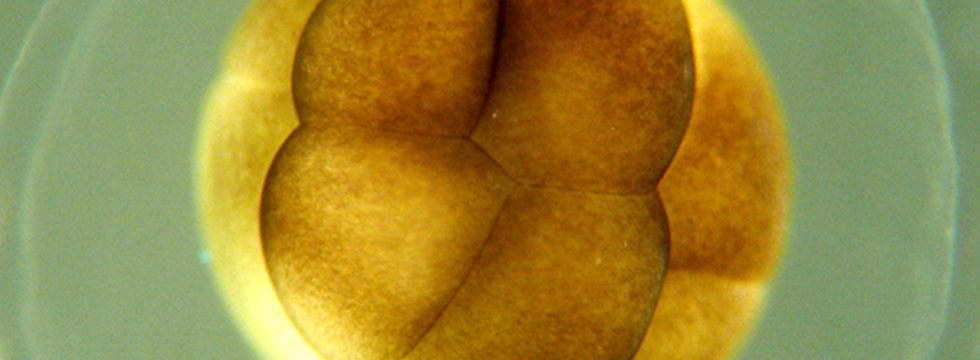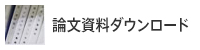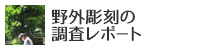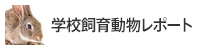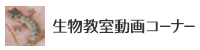シーナ・アイエンガー『選択日記』から抜粋
2003年4月のよく晴れた日のことでした。27歳の登山家アーロン・ラルストンは、あやまって360kgの巨大な岩とともに峡谷に落ち、右手を岩に挟まれてしまいます。かれは宙吊りのまま、岩から手を引っ張り出すこともできず、助けを求めて叫び続けました。
5日目には水が底をつき、死を意識するようになりました。遺言や遺品の分配について考え、家族への思いをビデオに録画しました。そしてもうろうとした頭でこう考えたのです。「こんなふうに自分が死ぬのを待つのは嫌だ。いっそ自殺した方がましだ」
ところが自殺の覚悟をしたとき、内なる声がこう言いました。
「本当に自分を殺すのか。ほかに選択はないのか」
彼はいま一度考えました。そして、心の中にあるあらがえない選択に気づき、それをはっきりと声に出して言いました。
「腕を切ればいいんだ」
自分で自分の手を切るのは簡単なことではありません。使える手は一本。ポケットに入っていたのは、切れ味の悪い5cmのナイフだけです。皮膚や筋肉をナイフで切りやすくするために、激痛に耐えながら、手で骨にヒビを入れます。それからゆっくり腕をナイフで切っていきました。多量に出血しながら10km歩いたところで、通りかかった人に救助されたのです。そのまま死ぬか、腕を自分で切り落としてでも、生きるか。酷い選択です。しかし、これはひとつの選択のありかたを極端な形で象徴しています。つまり、人生における選択は、すべて自由に選べるということなどありえず、かならず、その限界や、制約があり、見ようによっては、「選択」などしようがないじゃないか、と思える場合も多々あるということです。
私の場合がそうでした。学校の先生は子どもたちに、「あなたがたは何にでもなれる」と説きましたが、私はそれを聞きながら、様々な選択の限界を感じていたのです。実験の必要な化学や複雑な数式を読み解かなければならない数学を専攻することができるのか。そしてそもそも、普通の学校に行くことができるのか。しかし、こうした制約のなかでも、選択をすることはできました。
私は自分に課せられた制約をよくわかっています。しかし、その制約も、様々な角度から検討することで、見えなかった「選択肢」が開けてくるものなのです。