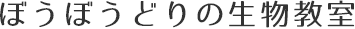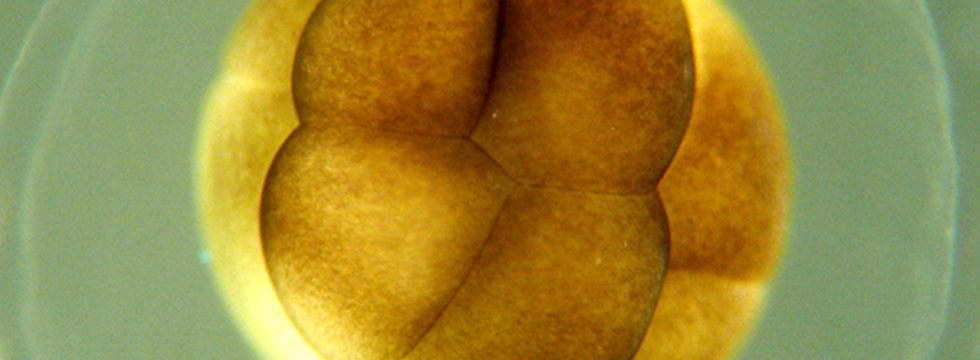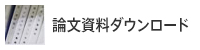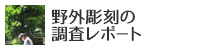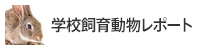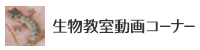田川健三氏の雑誌「指」から引用。
近ごろあまり「正しさ」ははやらない。これは危険な徴候である。はやらない理由はおそらく、人々が「正しさ」を押しつけと感じているせいであろう。むろん、すべての人々がそのようにしらけているわけではないので、ひたすら正しさを追求している人も多いけれども、残念ながら、全体から見ればそれはごく少数であろう。しかしそれよりももっと問題なのは、自分自身がどこまで正しさを追求し実践するか、という以前に、そもそも正しさの主張そのものに対して拒絶反応をおこし、嫌悪感をいだき、更には、あたかも正しさを主張することが悪いことであるかの如く眉をひそめたりする。ある意味では、昔から、本当に正しさを主張し実践する人はごく少数であった。けれども、それ以外の多くの人々も、自分で正しさを担い切ることはしないまでも、少くとも正しさを追求しなければならないと思っていたし、自分がそれを十分にやっていないということについてある種のやましさを感じていたし、従って、本気になって正しさを担って実践していく人がごく少数であったとしても、その人々をまわりから支える者はかなり多数であったし、直接支えることをしなくても、その人々はいわば無言の支持によって囲まれていた。無言の支持の部厚い層があったから、その人々はたとえ少数であっても、大きな力を発揮することができたのである。その意味では、自分がどこまでやれるかはとりあえず別として、本当は正しさを貰ぬかねばならないのだ、という感覚を多数の人々が保持していることが、まず重要なことであったのだ。
ところが最近の世相では、正しさを追求する人が孤立するだけでなく、まるで悪いことでもやっているかのように白眼視されてしまう。もっともそれも、とりたてて最近の世相というわけではなく、いつの時代でも、ある程度以上本気になって正しさを追求すれば、当然支配権力の非をならすことになるし、そうなれば当然何らかの仕方で弾圧抑圧される。従って、まわりの人々は、自分が弾圧抑圧にまきこまれたくないばかりに、正しさを追求する人を白眼視する、ということがおこる。これはいつの時代も変らぬ人情のいやらしさであろう。しかし、その場合でも、自分は正しさを追求していないというやましさは心のどこかにあるものだし、少くとも、たとえ自分に直接関わりのある現実においては積極的に正しさを担おうとする強をは持たないとしても、最少限一般論として、人間は本当は正しいことをやるべきなのだ、という意識だけは保っていた。最近の世相が特異なのは、人間は正しいことをやるべきものなのだ、という感覚が失なわれてしまったばかりか、そういう感覚を持っている人に対して、お前はおかしい、間違っている、変り者だ、けしからん、といった非難があぴせかけられる、という点である。これは非常に危険な徴候である。
こういう世相に対して、正しさの感覚を持つのがまっとうなのだということを論証したり説明したりするのは無駄である。人間は正しさの感覚を持つのがまっとうなのであって、どうしたらそういう感覚を持つことができるか、などと問うのは、おそろしく不当な問いである。そういうことを問うのは人間存在に対する侮辱なのだ。むしろ問うべきは、今の世相においてどうして人々はその感覚を失なってしまったのか、ということであろう。
正しさについての感覚が、いわば世論的なムードによって失なわれたについては、おそらく、さまざまな水準の異なった理由が相互に複雑にからまって働いている。だから、どの一つの原因を除去すればその状態が癒される、というような単純なことではあるまい。しかし多分、それらの理由の中でももっとも根本的なものの一つは、「正しさ」が見失なわれた、ということであろう。何が正しさであるかということがわからなくなると、やがて人々は正しさを追求することもやめてしまい、更には、正しさを追求する行為自体がくだらぬこと、良からぬことと思いこんでしまう。そういう状態は一朝一夕にして実現するものではない。ずい分長い歴史的過程の中で人々の精神が徐々にそういう方向に追いこまれていくのであって、従ってそれを回復するにも長い歴史的な努力を必要とするのかもしれない。かつて人々は、「八紘一宇」と称した帝国王義の精神を「正しさ」と信じた。それをむきになって信奉したのは一部の人だったにせよ、国民の大多数も、本気にならないまでも、何となく気分的にそれを「正しさ」と認める方向に傾いていたのは確かである。そして戦後、「正しさ」の尺度がひっくり返って、戦後民主主義の思想が民衆の正しさの基準となった。これも、それを本気になって信奉した人がどこまでいたかは別問題である。ファシズムの押しつける「正義」はむしろ無理な抑圧だ、と何となく感じていた人々が、ファシズムから解放されて、ほっとして、何となくこっちの方が正義だと思いこんだ、そこに戦後民主主義があった、ということだろう。だから、人々の精神の中で八紘一宇が必ずしも克服されたわけではなく、その結果、現在の教科書問題のような仕方でくすぶりつづける。これは決して文部省だけが悪いのではなく、非常に多数の日本人が何となくそのような史観を持ち続けている状態があるから、文部省がその上にのってあぐらをかいていられるのだ。そして、多くの人々が戦後の価値観の転倒の中で、ファシズムよりも戦後民主主義の方が有難い、よかったよかった、と胸をなでおろしつつも、「正しさ」の基準をつくるのは権力であって、権力が交代すれば「正しさ」も百八十度転換するのだ、という印象を持ってしまったのも事実である。戦後革命を民衆がみずからの力で実現したわけではない、ということの余波がこんなところにも現れる。「正しさ」とは外から権力をもって押しつけられることだ、という漠然とした印象がつちかわれる一つの根がここにあった。
その後、戦後民事王義の理想は絵に描いた餅だ、ということが徐々にはっきりしてくる。現実社会のさまざまな悪に抵抗し、さらに改革、変革していくには、それでは力にならない、ということがわかってくる。けれども、昔ながらの「左翼」は硬直した教条をふりまわすだけで、これが「正義」だ、と言われても、自分達の生活から離れたところで、自分達の主体性をぬきにして、教科書的に押しつけられた「理論」の言葉をうまく修得すれば正義にくみしているようなつもりになれる、というにすぎなかった。彼らもみずから教条主義の硬直に気がつきはじめたものの、その教条主義の体質はそのまま温存しつつ、ただそれを露骨に表に出さないように方針を転換したにすぎなかった。そこから出て来たのは、ごく目先のものを一つ二つ手に入れればいいというものとり主義であった。それが、現状に居直って、正義の追求などは仮空の世界のことだと思う心情を助長した。
他方、新しく出て来た左翼諸党派はそこのところを行動的に突破しようとした。けれども、極度な抑圧の状況の中で何らかの行動を突き出そうとすれば、どうしても他のことを犠牲にしてその一点だけに集中する、ということになる。これは、やむをえなかったことだし、そうしなければ何の行動も生み出せないという状況が一般的であったから、そこを突破して何かをやろう、というのは正しかった。しかしそれが裏返しになると、行動の教条主義になる。他のことを犠牲にしてでもこの一点に集中しようというのは正しいが、他のことを犠牲にしてこの一点に集中しないのは悪い奴だ、となったら、その 「正義」は暴力になる。
こうして、歴史的にさまざまの要因が重なって、「正しさ」とは外からもしくは上から押しっけられる庄力にすぎない、という感覚が蔓延するようになった。けれどもそれだけでこうはならない。基本的には、国民のそういう精神状況の上に居座ってうまい汁を吸っている者達が、好んでそういう精神状況を助長しょうとしているのである。しかも国民の大多数も、自分も一緒にうまい汁を吸える側にいるのだと思いこんでいるので、「正しさ」を追求することによって状況を動かそうなどとは思わない。自分達の既得権(それはべらぼうに巨大で、従って著しく不当なものから、ごくみみっちいものまで多種多様)に居座って、動こうとしない。後者の場合、保証されている僅かなみみっちい既得権よりも、侵害されている権利や自由の方がよほど多いのだが、侵害されているという意識さえ持たなくなっており、従ってそれを取りもどす「正しさ」のために立ち上ろうとせず、ただ現状維持にしがみつく。正しさの追求とは、現状を正しさの方向にむけて変更することである。従って、現状維持の心性に慣れきった人達は、正しさの追求に背をむけ、むしろ正しさを憎悪する。
この状態を回復するのは容易なことではないが、とりあえず二つ三つのことを言っておこう。
第一に、何が正しいのかわからないということと、正しさが存在しないということは、同じではない。ところが、そこがしばしば混同される。何が正しいのか自分で主体的に見きわめることができなしなっている場合、「正しき」は外側から何らかの力によって押しつけられるものと思えてくる。そうなると、押しつけられた事柄は正しさとは思えなくなる。そしてついに、「正しさ」というのは自分勝手な判断を他人に押しつけることだと思いこんでしまう。現にそのように思いこむ若い人が非常にふえているのは事実である。確かに、以上述べたような歴史的経過からしても、またそれとはやや水準の違う問題だが、近頃の学校教育がやたらと規律と教育内容を強権的に押しつけることに終始していることからも、若い人達がそのように思いたくなる気分を理解できないわけではない。しかし、それでほっておいていいということにはなるまい。所詮何が正しいのかわかるはずがない、などと言って居直る怠慢さは、弱肉強食の地獄へとつっ走るお膳立にしかならない。我々はやはりロをすっぱくして、何が正しいのかを自分(達)が判断できない場合があろうとも、正しさは厳然として存在しているのであって、自分がそれを発見できないだけなのだ、と指摘していかねばならぬ。今この瞬間に何が正しいのかわからないとしても、わからないままに自分のなした行動が(あるいは、わからないから何もしなかったという「行動」が)、結果において偶然正しかったということもあるし、逆にひどく不当であった、ということもある。本人(達)がわかろうとわかるまいと、正しいことは正しいので、正しくないことは正しくない。これは個々人の行動から社会全体にかかわるようなことにいたるまで、どの水準にわたってもそうである。もしも押しっけられた「正しさ」が正しくないのなら、自分で自立して正しさを見つけていかねばならぬ。たとえ見つからないとしても、あるいは見つけることをさぼってそっぽを向いていようとも、我々はやはり毎日、正しいことをしたり悪いことをしたりして生きているのである。そうであるならば、たとえ完全に正確に正しさを把握することができないとしても、できる限り正しさに近いものをとらえようとすべきであろう。入間は、「正しさ」の問題にそっぽをむいて生きることはできる。しかし、事実として正しさの問題を離れて生きることはできないのだ。
第二に、正しさの問題は、何か天下国家の動向にかかわるような水準のこととは限らない。そういうこともあるが、ごく卑近な日常の一挙手一投足がすべて正しさの問題である。明日の朝何時に起きようか、ということにしても、会社に遅刻してはいけないからきまった時間に起きよう、というのが正しいかもしれないし(それが会社に対する忠実さであるとは限るまい。会社の中できっちり闘うには、まず自分がきっちり存在している必要がある)、あるいは、そういうことを気にするのは愚劣なので、目がさめるまで寝ていよう、というのが正しいこともある。女房より先に起きて朝飯をつくらないと、というのもあるし、ほかにもいろいろあろう。そして、たかが朝起きることだけでも、現在の社会状況全体と常につながっている問題なので、正しさの問題を追求していけば、常に社会状況全体の正しさと関わらざるをえなくなる。一つの正しさが他の正しさとからまりあい、一つの正しさだけを突出して追求することが正しくないこともあり 他の正しさを犠牲にして突出することが正しいこともある。我々のあらゆる一挙手一投足に、その一つずつに、無数の正しさの問題がからまり続けている、と言ってよい。その中で総合的な正しさを、できるだけ近似的に正しく、常に追い求めていくはかない。そんなことをしていたら、緊張で疲れ切ってしまう、と言われるだろうか。私もそう思う。だから、ひどく疲れないように適当にさぼって寝ているのも、しばしば正しい。
第三に、ここでもまたぞろ主観客観の問題が出てくる。事実はすべて客観的に中性であるのだが、その事実が正しいかどうかは、見る人の主観的な視点によって異なる、という例の思想(というより妄想)である。だから、「正しさ」は主観の問題であって、自分の主観でしかないことを他人に押しつけてはならぬ、というのだ。これは嘘である。事実として正しい事実があり、けしからん事実がある。中にはどうでもいい事実もあるが〉 だからといってすべてがどうでもいいわけではない。正しい行為が、見る立場によってはけしからん行為になる、ということはないし、けしからん暴虐の行為が、見る立場によってはどうでもいい事実になる、ということもない。確かに、同じ事実が見る人によって正しいことに見え、他の人にはけしからぬことに見える、ということは常にある。だからと言って、事実の正しさは主観の問題だということには決してならない。その場合、どちらか一方が間違って見ている、というにすぎないのだ。どちらも間違っている、ということも多かろう。だが、それをよく見ぬく人がいようといまいと、事実の正しさに変りはないのだ。