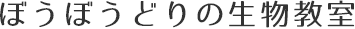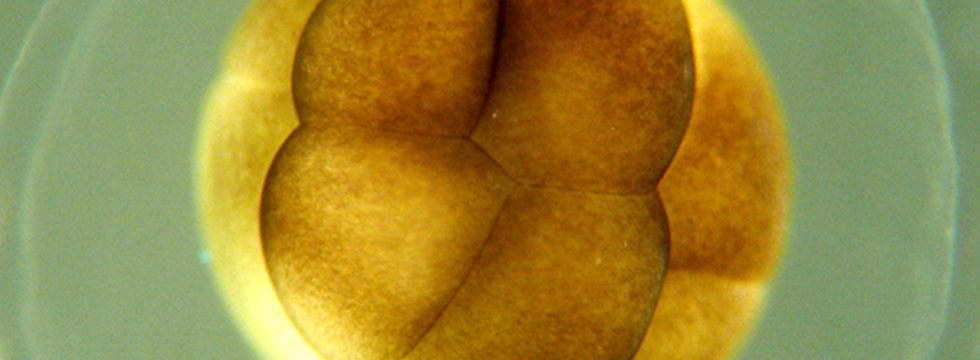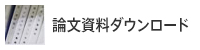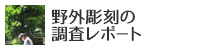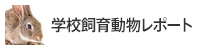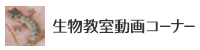『知能神話』(山下恒男・1980)より抜粋
“わかる”とか“できる”というのはいったいどういうことなのだろう。子どもとつきあっているときに、しばしばこのことを考えさせられる。子どもがものと親しくふれ合いながらそれを自分の中にとらえこんでいく営みは、実に多面的で豊かな顔をもっているからだ。
たとえば、幼稚園児は同じ椅子がたくさん並んでいる中から、自分の椅子をちゃんと見分けることができる。家庭の中でも、数人のきょうだいが大人には同じようにみえるハソカチや消しゴムを、「自分のはこれだ」と迷わずに“わかって”いる風景はよくあることだし、父親が自動車で帰宅したときに、「あっ、お父さんの車の音だ!」とすばやくその音を聞き分けるのも、たいてい幼い子どもである。ものと子どものこういう親密な“わかりかた”は、心理学者ウェルナーが「相貌的知覚」と名づけた知覚のスタイルに属している。(『精神の発達』岩波書店)
それはふつう、「原始的な」心性とよはれている。このような“わかりかた”は単に子どもばかりではなく、「原始的な」心性をもつといわれる人々、たとえばアフりカの原住民などにもみられる。彼らが抽象的な数としては“3”くらいまでしか理解しないにもかかわらず、数百頭の牛のなかの一頭がいなくなったことをすぐに発見する能力がそれに当る。数百頭の中の失踪した一頭は、数としての1ではなく、その牛なのである。そのような“わかりかた”のできる人々にとって、抽象的な高度な数概念は生活の中に必要とされない。そして彼らのもつ能力は逆に、西欧近代文明の中に生きる私たちの中からは非常にうすれてしまったものである。私たちは“わかる”という言葉を、しばしばたいへん気易く使っているけれども、少し立ち止って考えてみると、この言葉はなかなか深い問題をもっていることがわかる。