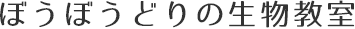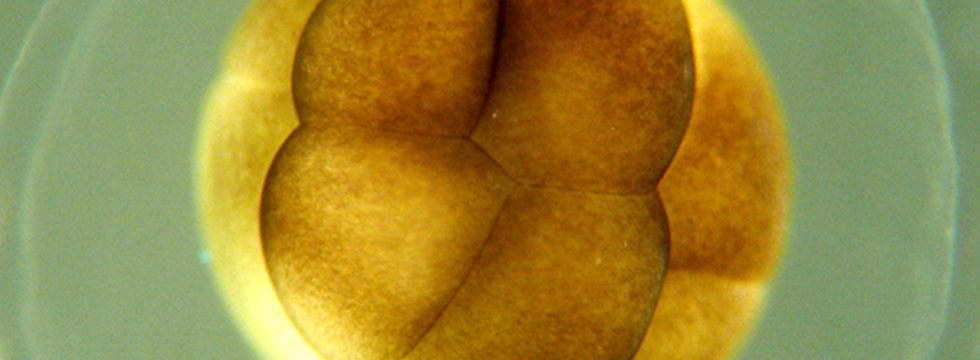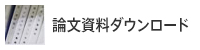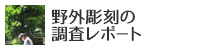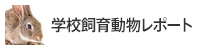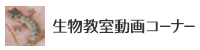16歳のとき作文に「死」という題を出されて「死とはスフィンクスである」と書いた。生がわからないから死がわからず、何もわからないから、わけのわからないものを持ち出したのであった。それからの30余年問に、見すぎるほどに多くの死体を見た。たとえば、某医科大学の記念祭にならべられていた病死者3000余体の各部分。犯されてしめ殺された事件現場の、娘の苦悶のしたたり。白人兵に斬り刻まれたアジア人のからだの、まるで解剖図絵のようなもの。その上に舞っていた青バエ。肉親の号泣。両手にすくわれてしまうほどの少量であったのに、どうしてあんなに重かったのか、幼女のコツ。累々とかさなっていた被爆焼死者たちの炭化現象。場景はどうであろうと、哀痛の涙も憤怒の唾も、液体はみなかわいて消えた。どの死体も、丁寧に扱われようが粗末に扱われようが、みなどこかへ運ばれていって消えた。死者をかこんだ生者たちの、生きておるがゆえのおしゃべりは聞きあきた。もう繰り返さないという約束ごとが繰り返し反故にされていくことこそが、スフィンクスとなった。状況はいまもって一六歳の当時と大差がなく、何はできなくとも精いっぱい長生きして見届けるだけでも値打ちがあると居直ったり、いや、そうではない、適当の門限に消えていくことが人間としてのつとめの完了だとじれたりするのだが、しょせん生がわからなければ死がわかるはずはない。生きて生きて生きぬくことなしに、どうして生の意味が、死の意味がわかろうか。死んだもののようにだまりこくって生きているわれわれ大群衆が、たしかに生きていることのあかしをたてる日のほかに、いつに期待できようか。