
- 清心女子高等学校 秋山繁治 生態調査の方法 生態調査では,標識再捕法がよく使われてきた。標識再捕法は,調査地域の個体群の一部を捕獲し,標識をつけてから放し,再捕獲して,再捕獲したときの標識個体の割合から全体を推定する方法としてよく知られている。また,一定の時間を経過した後の再捕したときの位置情報から,移動方向や距離を調べることによって,季節移動のパターンなどを調べるのに使われてきた。標識は,昆虫…続きを見る









2004年11月17日

2004年8月 5日
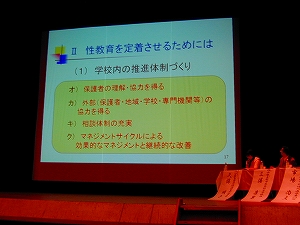
2004年1月 1日





2003年5月10日

2002年7月 1日

1999年10月12日

1999年8月 5日

1999年5月31日






